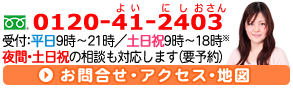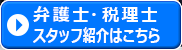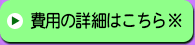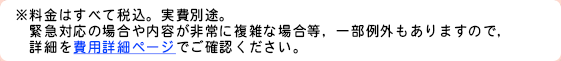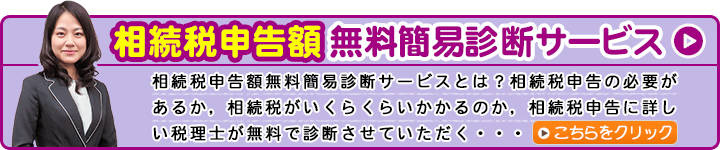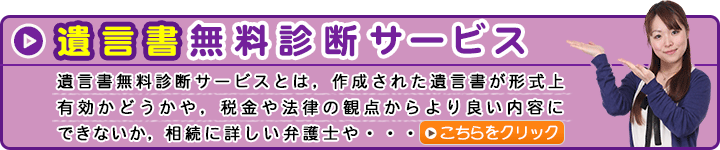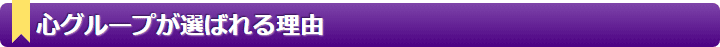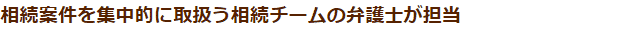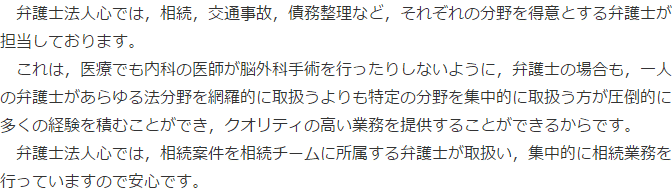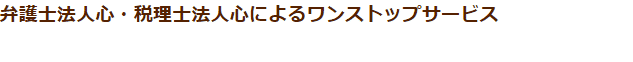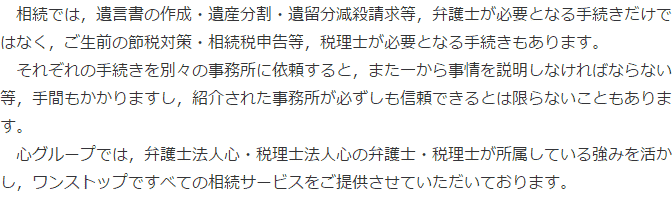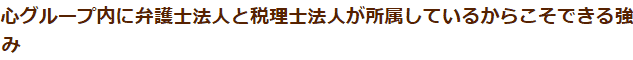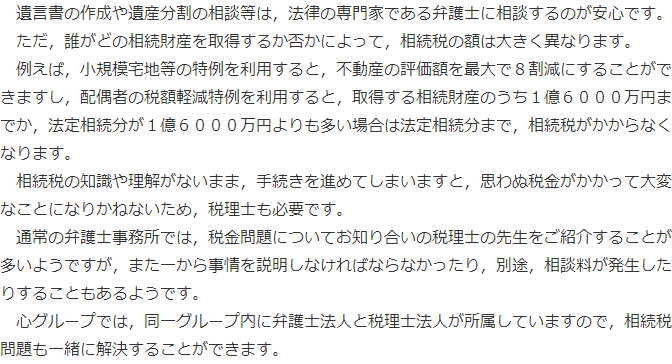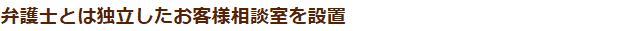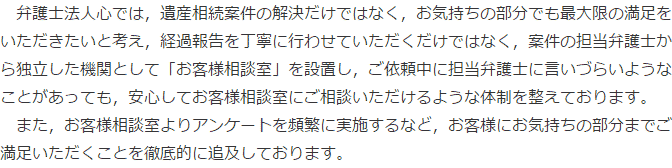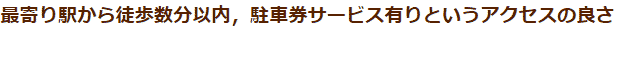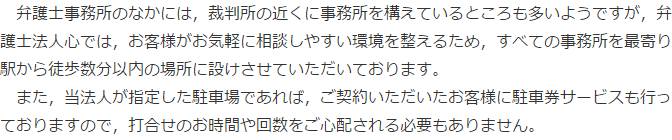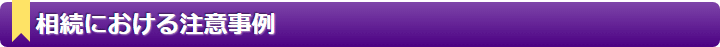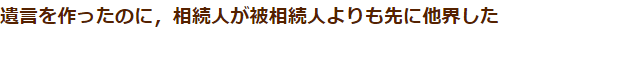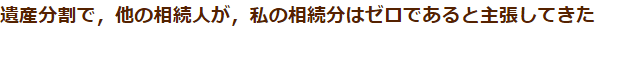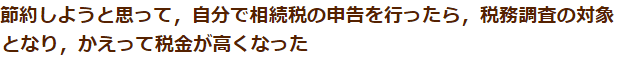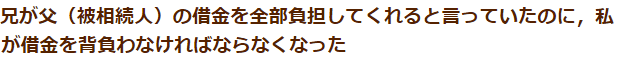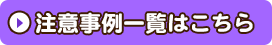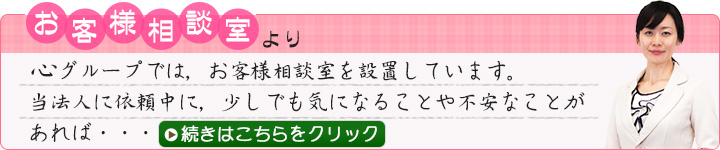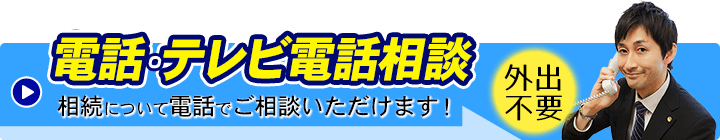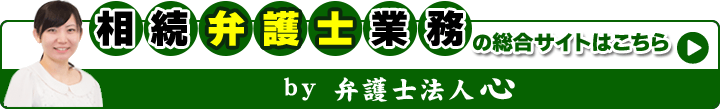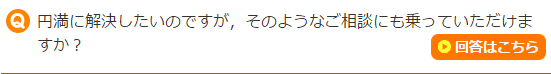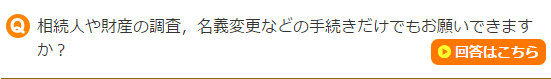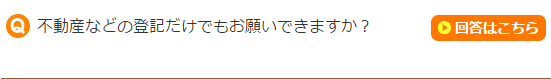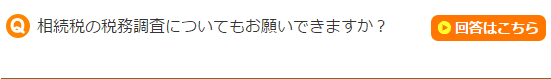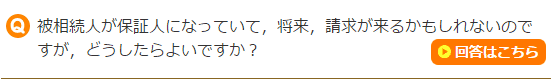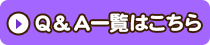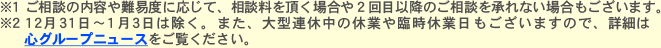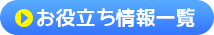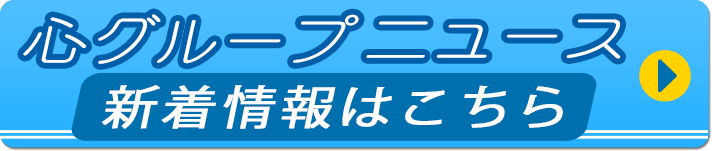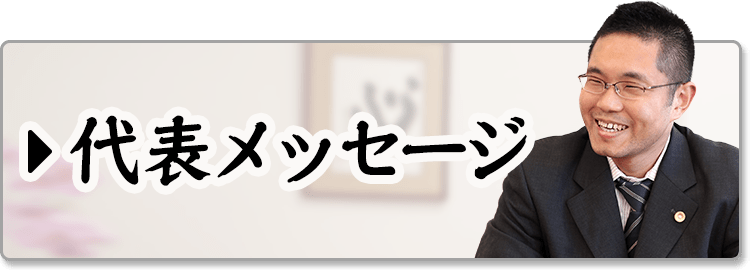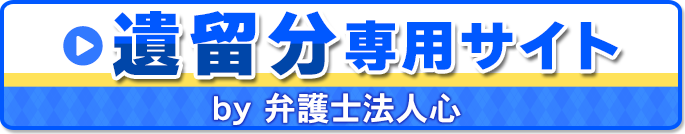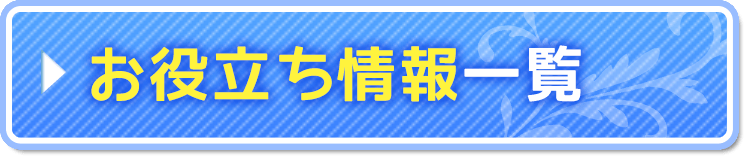業務内容
四日市で相続についてお考えの方へ
私たちの相続への取組みの特徴などについて紹介しています。相続についてのご相談をお考えの方はご覧ください。
相続の上で気を付けること
相続では、被相続人が連帯保証人となっているなど、想定外のことが起こり得ます。相続の注意事項について紹介していますので、ご一読ください。
対応エリアのご案内
便利にご相談いただける立地に事務所があります。詳しいアクセスはこちらからご覧いただけますので、ご相談前にご確認ください。
相続に強い専門家に依頼するメリット
1 相続問題は情報の勝負になる

相続問題は、情報の勝負になることが多々あります。
相続に関する情報をもっているかどうかによって、最終的な解決の内容が大きく異なってくる可能性があります。
そして、必要な情報をどれだけ得られるかは、専門家によって大きく異なってきます。
相続に強い専門家であれば、必要な情報を十分に得られる可能性が高まり、より妥当な解決へとつながる可能性が高いです。
2 複数の専門家の領域にまたがる情報が必要になる
ここで注意しなければならないのは、相続で必要となるのは、複数の専門家の領域にまたがる情報であることが多いということです。
相続は、法律の話だけが問題になるわけではなく、税金の話や不動産の知識が必要となることがあります。
例えば、不動産の相続が問題になった場合は、不動産を誰が取得すべきかだけが問題となるわけではありません。
相続分との関係では、不動産の価値をどのように評価すべきかが問題になります。
また、不動産を売却することが予定されている場合は、不動産の売却方法や、売却に伴う経済的負担も問題になってきます。
さらに、不動産の相続・売却では税金が発生することもあります。
このように、相続には複数の領域が関わるケースがあるため、幅広い情報が求められます。
3 どのような専門家に依頼すべきか
以上の点を踏まえると、複数の領域をカバーしている専門家、複数の専門家で連携して対応することができる専門家が、相続に強い専門家であるといえます。
もちろん、1人の専門家があらゆる領域に精通していれば、それは大きな強みになるでしょう。
とはいえ、相続においては非常に幅広い知識や経験が求められるため、1人の専門家があらゆる領域に精通するというのは、現実的ではありません。
また、1人の専門家があらゆる領域に精通していなかったとしても、複数の専門家が連携することができれば、それぞれの専門領域をカバーすることができます。
そのため、複数の領域にまたがって連携できる専門家に依頼することができれば、網羅的に情報を得ることができ、よりよい解決に導くことができるでしょう。
相続の生前対策をお考えの方へ
1 相続の生前対策は、様々な専門家の領域が絡み合っている

相続の生前対策には、様々な専門家の領域が絡み合っているため、1つの専門家の考えに基づいて生前対策を行ったとしても、他の専門家から見ると、不適切な生前対策になってしまっているといったことが起こり得ます。
相続の生前対策では、複数の専門家の考え方を総合し、最も適切な対策をとることが必要です。
ここでは、1つの専門家の考えによって生前対策が行われた結果、取り返しのつかない事態が生じてしまった例を説明したいと思います。
2 相続税対策のため、自社株式の分散が行われた事例
この例では、会社経営者が有する自社株式について、相続税対策が取られていました。
会社経営者が税理士に相談したところ、自社株式を少しずつ安価で第三者に譲渡するのが有効であるとのアドバイスがなされました。
自社株式を第三者に譲渡することで、会社経営者が有する株数を減じることができ、会社経営者が有する資産(将来の相続財産)を減少させることができます。
また、自社株式を少しずつ第三者に譲渡する場合には、配当還元方式という評価方法を用いることができます。
このため、配当が少額または0円である場合には、自社株式の評価額を抑えることができ、税負担を抑えつつ、自社株式を第三者に移転することができます。
この結果、この会社は、何十名もの少数株主が存在する状態となり、会社経営者が有する株式の割合が、発行済株式総数の3分の2を割り込んでいました。
このため、有事の際に特別決議を行わなければならない場合には、少数株主に対しても株主総会の招集通知を行った上で、3分の2以上の株主の同意を得なければならない状態になってしまいました。
こうした状態を解消するため、後継者の代になってから、少数株主からの株式の買取を進めることとなりましたが、後継者の代は、会社の株式の評価額がさらに高額になっており、株式の買取のため、かなりの支出を要する状況に陥っていました。
結局、株式の買取のための資金調達の目途が立たず、株式の買取の計画については、断念せざるを得なくなってしまいました。
相続の生前対策を行うに当たっては、相続税を軽減するという観点だけでなく、将来の会社経営の安定化等の観点も必要であったと言うことができます。
そのためには、弁護士等の法律の専門家のアドバイスも得ておく必要があったと言えます。
3 生前対策のご相談をお考えの方へ
私たちは、複数の専門家が必要に応じて協力できる体制を整え、相続に関する相談をお受けしています。
複雑なご相談にも対応可能ですので、相続の生前対策にお悩みの方はご相談ください。
遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割は法的知識が重要

どのように遺産分割を行うかについては、相続人全員が合意を行えば、基本的には、自由に決めることができます。
このため、相続人全員が合意することができるのであれば、特定の相続人が多めに遺産を取得することも、それぞれの相続人が均等に遺産を取得することも可能であるということになります。
とはいえ、相続人がどのように遺産分割を行うかを決めるにあたっては、法的知識を持っているかによって、円滑に話し合いが進むかどうかが違ってくるのが実情です。
以下では、このことについて、場合分けをして、具体的な理由を説明したいと思います。
2 特定の相続人が多めに遺産を取得することとする場合
特定の相続人が多めに遺産を取得するという遺産分割を行うケースは、現在でも、時々あります。
もっとも、近年では、法律上は相続分をベースに遺産分割を行うこととなるという考え方が浸透してきています。
そのため、初めから特定の相続人が多めに遺産を取得するとの前提で話合いを進めてしまうと、他の相続人の心情を害してしまい、遺産分割協議がスムーズに進まなくなるおそれがあります。
特定の相続人が多めに遺産を取得すべき法的な裏付けとしては、例えば、以下のようなものが挙げられます。
① 他の相続人がすでに被相続人から贈与を受けている
他の相続人がすでに相続人から贈与を受けている場合には、その相続人に特別受益が存在し、その相続人の相続分が減じられる可能性があります。
② 特定の相続人が被相続人の財産の形成・維持について特別の貢献を行った
特定の相続人が被相続人の財産の形成・維持のため、特別の貢献を行った場合には、その相続人に寄与分が認められ、その相続人の相続分が増加する可能性があります。
3 それぞれの相続人が均等に遺産を取得することとする場合
それぞれの相続人が均等に遺産を取得することとする場合では、何をもって均等に遺産を取得したものと考えるかについて注意が必要となります。
遺産が現預金や有価証券といった金融資産だけであれば、価値をある程度客観的に判断することができるため、あまり問題が生じることはありません。
他方で遺産に不動産が含まれている場合には、その不動産の評価額をどのように計算するかが問題となる場合があります。
このような不動産の評価方法について、あらかじめ法的な知識を得ておくと、遺産分割協議がスムーズに進む可能性が高くなります。
4 遺産分割でお悩みの際は私たちにご相談ください
以上のとおり、遺産分割では、あらかじめ法的知識を得て、協議に臨むことができるかどうかが重要な分かれ目になってくることがあります。
相続で遺産分割を行うことになりましたら、お早めにご相談いただければと思います。
遺言についてお悩みの方へ
1 遺言を作成する際には、将来のシミュレーションが必要

遺言を作成すると、将来、残された方々に、どのように相続財産を引き継ぐかを定めることができます。
遺言は、将来のことを想定して作成されるものであるため、残された相続人の将来の生活、相続人間の関係等、様々なことを想像して、内容を決める必要があります。
特に、作成した遺言について、将来、どのような法律問題が発生する可能性があるかについては、しっかりとシミュレーションをしておく必要があります。
ここでは、将来のシミュレーションが必要な法律問題の例として、遺留分の問題を説明したいと思います。
2 遺留分侵害額請求がなされた場合を想定する
遺言については、特定の人がすべてまたは大部分の相続財産を取得するとの内容のものが作成されることが多くあります。
しかし、このような遺言を作成すると、実際に相続が起きた後、相続財産を取得しなかった相続人から、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。
⑴ 遺留分とはどのようなものなのか
相続人は、法律上、相続財産について最低限主張できる権利を有しています。
遺言を作成したとしても、各相続人は、この最低限の権利を主張して、財産を取得した相続人に対し、一定の金銭の支払を請求することができます。
このような、相続人が相続財産について主張できる最低限の権利を、遺留分と言います。
遺留分は、子や配偶者が相続人の場合は、子や配偶者の法定相続分の2分の1になることが多いです。
⑵ 遺留分の主張がなされた場合の対応
ここで注意しなければならないのは、2020年に施行された改正相続法により、遺留分の主張がなされた場合は、遺留分を主張する相続人に対しては、遺留分に相当する金銭の支払をしなければならない、とされたことです。
このため、法律上は、金銭の代わりに、取得した相続財産のうちの不動産を分けるといった対応は、できないこととされてしまいました。
したがって、遺言により財産を取得した人は、遺留分権利者との合意が成立しない限り、遺留分に相当する金銭を準備し、遺留分権利者に対する支払をしなければならないことになります。
⑶ 相続財産で不動産が占める割合が大きい場合の問題
相続財産について、金融資産が占める割合が大きい場合は、金融資産の払戻を行い、遺留分権利者に対する支払を行うこともできますので、問題が少ないのですが、不動産が占める割合が大きい場合には、別途、遺留分に相当する金銭を準備しなければならないこととなりますので、どのようにして金銭を準備するかが、切実な問題になってきます。
このように、2020年に施行された改正相続法により、遺言により財産を取得した人は、遺留分侵害額請求がなされることにより、かなり追い込まれた状態となることが起き得る状況となっています。
⑷ 遺言を作成する際に考慮すること
以上を前提とすると、たとえば、相続財産のすべてまたは大部分を特定の相続人が取得するとの遺言を作成するのではなく、遺留分を主張する可能性のある相続人に対しては、不動産を現物取得させることとするといった遺言を作成するといった対応も、考えなければならない状況となってきています。
このため、遺留分の主張がなされる可能性がある場合は、誰がいくら程度の遺留分の主張を行い、これに対して、どのように対応するのかについて、将来のシミュレーションを行っておくことが望ましいと言うことができます。
このような将来の問題について、十分なシミュレーションを行うには、専門家に相談するのが望ましいでしょう。
遺言の作成をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄は時間との勝負になる

相続放棄をお考えの場合は、できる限りお早めに専門家へご相談ください。
相続放棄は、基本的には、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に、管轄権のある家庭裁判所に、申述書を提出することにより行う必要があります。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
3か月の期間が経過してから相続放棄を行おうとしても、原則として、家庭裁判所が申述を受理することはありません。
例外として、相続財産と相続債務の存在をまったく知らなかった場合には申述が受理されますが、こうした特別の事情がなければ、申述が受理されることはありませんので注意が必要です。
この3か月の期間は、意外に短く、期限までに申述を行うことができるかどうかが問題になってくることもあります。
以下では、このような実例を説明し、相続放棄が時間との勝負であることを説明したいと思います。
2 相続財産の存在を知っていたが、相続債務の存在を知らなかった事例
この事例では、相続人は、被相続人が亡くなったことについては、当日に知っていました。
また、被相続人が自宅の土地、建物を所有していることも熟知していました。
その後、被相続人が亡くなってから2か月半が経過した頃、信販会社から、被相続人に500万円の未返済の債務があること、相続人に対して返済を求めることを内容とする通知が届きました。
先程の説明から、相続人は、自宅の土地、建物が相続財産であることを熟知していたこととなりますので、相続財産の存在を知ってから3か月の期間が、わずか2週間後に迫っている状況でした。
この事例では、相続人は、期限の1週間前に弁護士に相談を行い、弁護士が短期間で申述書等を準備し、家庭裁判所に提出しましたので、事なきを得ました。
相談が少しでも遅れていたら、期限が過ぎてしまっていた可能性もありました。
3 被相続人の最後の住所が分からなかった事例
この事例では、被相続人の甥姪が相続人でした。
相続人は、被相続人との交流がなく、被相続人がどこで生活していたのかも知りませんでした。
ある日突然、相続人宛に、被相続人の債権者を名乗る人物から、被相続人の債務の返済を相続人に対して求めるとの通知が届きました。
相続人は、事情が分からなかったため、債権者に連絡を取りましたが、債権者は、返済を求めるとの一点張りでした。
このような状況であったため、相続人は、相続放棄を行うことを決意しました。
ところが、ここで1つ問題が発生しました。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することにより行います。
例えば、被相続人の最後の住所が四日市だったら、四日市にある家庭裁判所の支部に提出することになります。
相続人の場合は、被相続人との交流がなかったため、被相続人の最後の住所がどこだったか分からず、どの家庭裁判所に申述書を提出すれば良いのか分かりませんでした。
その後、相続人は、弁護士に相談しました。
弁護士は、被相続人の住民票の除票を取得して、被相続人の最後の住所を特定することを提案しました。
しかし、被相続人の最後の住所を特定するためには、順次、相続人の親の戸籍、相続人の祖父母の戸籍、被相続人の最後の戸籍を取得しなければならず、かなりの時間を要しました。
最終的に、3か月の期間が経過する直前に、被相続人の住民票の除票を取得することができ、被相続人の最後の住所を特定することができましたので、管轄権のある家庭裁判所を特定することができました。
この事例も、少しでも相談が遅れていたら、期限内に相続放棄の申述を行うことができない可能性がありました。
4 ご相談はお早めに
このように、相続放棄については、時間との勝負になることがしばしばあります。
「まだ期限まで余裕があるから大丈夫」と思っていても、予期せぬ事情により、期限内に相続放棄を行うことができないといったことも起こり得ます。
相続放棄をお考えの方には、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
遺留分を請求したいとお考えの方へ
1 遺留分を請求する期限に注意する

遺留分侵害額請求については、法律上、期間の制限が設けられています。
具体的には、遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に、遺留分侵害額請求を行う意思表示をする必要があるとされています。
この1年の期間が経過した後に遺留分の主張を行ったとしても、遺留分の権利は時効によって消滅してしまいます。
遺留分が侵害されている事実を知ってから1年間とは、多くの場合、遺言の存在を知ってから1年間になります。
2 期限までに何をしなければならないか
ここで注意したいのは、後日、遺留分侵害額請求を行う意思表示を1年の期間内に行ったことを、どのように証明するかということです。
一般的には、相手方に対して内容証明郵便を送付し、相手方がいつどのような郵便を受け取ったかということを、郵便局の証明を通して客観的に明らかにしておくということです。
しかし、近年では、遺留分の時効の存在が広く知られつつあることに伴い、1年の期間が経過するまで、郵便の受け取りを拒否したり、所在不明の状態にしたりしておき、期間が経過するまでやり過ごそうという対応をとる相手方が、散見されるようになってきています。
このような場合には、期限内に相手方に内容証明郵便を送付することができず、遺留分の権利が消滅することとなってしまいかねません。
そのような場合に備えて、相手方が内容証明郵便の送付を阻止するといった対応をとることを想定しつつ、どのようにして期限内に意思表示を行ったことを客観的に明らかにするかを検討する必要が生じてきています。
このような場合には、相手方の就業先に郵便物を送付する(ただし、相手方のプライバシーを侵害しないよう、送付方法について留意する必要があります)、公示による意思表示を行うといった対応が考えられます。
もっとも、こうした対応を検討したり、実施したりするためには、時間を要します。
期限の1週間前に相手方が所在不明の状態になっていることが明らかになったとしても、期限内に手続をとることができない可能性が高いです。
この点を踏まえると、遺留分侵害額請求を行う場合は、期限の直前に行動に移るのではなく、1か月程度の余裕を見て行動に移る必要があると言えます。
3 遺留分侵害額請求を検討する場合はお早めにご相談を
以上の理由から、遺留分の請求を検討される場合は、時間的にある程度の余裕を見て相談されることをお勧めします。
私たちは、相手方が所在不明になっていた案件も含め、遺留分についての様々なご相談をお受けしていますので、遺留分についてのご相談事がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
相続税についてお悩みの方へ
1 相続税申告を行うには、法令、通達、実務等を熟知している必要がある

相続税は、他の税目と比較して、法令、通達、実務等で、詳細なルールが定まっているという特殊性があります。
また、こうしたルールは極めて多岐にわたるため、都度調べながら申告書を作成すると、ルールの見落としが生じがちです。
こうした、極めて多岐にわたるルールを熟知していなければ、誤った申告書が作成されてしまいかねません。
そして、誤った申告により、過大な相続税を納付することとなってしまえば、過大に納付した分が、そのまま損失となってしまいます。
また、誤った申告により、過少な相続税の納付になってしまった場合は、後日、税務署から、誤りの指摘がなされ、本税を追加で納付しなければならないばかりか、加算税や延滞税も納付しなければならなくなってしまいます。
こうした事態を避けるためには、法令、通達、実務等を熟知した専門家に相続税の申告を依頼することをお勧めします。
2 法令、通達、実務等を熟知した専門家とは
それでは、法令、通達、実務等を熟知した専門家かどうかは、どのようにして見分ければ良いのでしょうか。
質問に対する受け答えで判断することができる場合もありますが、多くの場合、専門家がどの程度熟知しているかを判別することは、困難を伴うものと思います。
ここでは、いくつかの外形的な判断基準を挙げたいと思います。
① 特化した専門家かどうか
実情をお話しすると、多くの税理士は、相続税申告については、年間1件受任しているかどうかです。
相続税に特化し、年間でまとまった件数の相続税申告を行っている税理士は、実のところ少数派です。
このように、相続税に特化した専門家かどうかは、1つの判断基準になります。
② 専門家の側から問題提起ができるかどうか
専門家によっては、受け取った資料の数字を拾うだけで申告書を作成してしまうといったことがあり得ます。
しかし、実際には、受け取った資料には、様々な手掛かりが存在しています。
このような手掛かりを見つけ出し、専門家の側から問題提起を行うことができるかどうかによって、ルールを熟知している専門家かどうかが判断できることもあります。
3 私たちにお任せください
私たちにご相談いただければ、相続税申告に特化した専門家がお悩みをお伺いし、対応させていただきます。
相続税案件を集中的に扱っている者が迅速かつ適切な事案解決を目指して対応いたしますので、私たちにお任せください。
相続税についてのご相談を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
相続について税理士に相談するべきタイミング
1 初回相談については、早めの相談を

相続が発生すると、相続税の申告をしなければならないことがあります。
具体的には、相続財産の価格が、3000万円+法定相続人数×600万円を超える場合は相続税の課税対象になる可能性があり、申告を検討する必要が出てきます。
参考リンク:国税庁・相続税の計算
相続について税理士に相談すべきタイミングは、初回相談は早ければ早いほどよいといえます。
多くの場合、相続税の申告は、人生で1、2度あるかないかだと思います。
相続税の申告から納付までの流れについて、まったくイメージがわかず、いつ、どのようなことをすれば良いのか分からないことも多いのではないでしょうか。
そのため、まずは、相続税の案件を多く取り扱っている税理士にご相談いただき、相続税の申告から納付までの流れについて、早いうちにイメージを掴んでいただくことが重要だと思います。
相談をした時期が遅かったため、期限までに間に合わなかったといった事態を避けるためにも、まずは、お早めに税理士へご相談ください。
2 2回目以降については、ケースバイケース
2回目以降の相談のタイミングについては、ケースバイケースだと思います。
ただ、次のような場合には、2回目以降も早めにご相談いただいた方がよいのではないかと思います。
① 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を利用する場合
この場合には、特例を適用する前提として、遺産の帰属が確定している必要があります。
もし、遺言が存在しないのであれば、相続人全員の同意により、遺産分割協議を成立させる必要があります。
また、小規模宅地等の特例の対象となる土地が複数ある場合には、これらの不動産を取得したすべての相続人が、どの不動産に特例を適用するかについて同意を行う必要があります。
このように、相続人全員の同意が必要になるため、早めにご相談いただき、特例を適用するための協議を行っておくのが望ましいです。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
② 物納を行う場合
相続税においては、一定の要件を満たしている場合には、金銭ではなく相続財産の物納で税を納めることができます。
物納を行う場合は、物納の準備のため、一定の期間を要します。
例えば、不動産を物納する場合は、その不動産が測量済みであること等、一定の要件を満たす必要があります。
測量を行うには、隣地所有者全員の同意が必要となりますので、長ければ3か月程の期間を要することもあります。
また、物納を行うにあたっては、国税庁の許可を得る必要があるため、許可申請書の準備や許可手続きのための時間も必要となります。
そのため、この場合にも、なるべく早めに税理士に相談しておくとよいでしょう。
参考リンク:国税庁・相続税の物納
相続の無料相談をお考えの方へ
1 相続は落とし穴が多い

書店には、相続に関して説明している書籍は多数あります。
また近年では、ネットで情報を得ることも容易になってきているため、相続に関する情報に触れることができる場面は多くなっているといえます。
しかし、相続に関する情報を容易に得ることができるようになった一方で、「相続は単純な話である」「簡単に手続きを進めることができる」といった誤解が生じてしまっています。
加えて、書籍やネットの記事には、誤った情報が含まれていることがあります。
近年では、ネットや書籍で得た知識をもとにして、相続に関する様々な主張がなされることがありますが、その内容が実は誤りであったというようなことが散見されます。
専門家であっても、落とし穴にはまってしまい、誤った知識に基づいて主張してしまうということも起こり得ます。
相続について、一見すると、単純な話である、簡単に手続きを進めることができるとの印象を抱くかもしれません。
しかし実際は、様々な落とし穴が潜んでいる分野です。
ここでは、こうした落とし穴の1つを紹介したいと思います。
2 遺留分は相続分の2分の1?
遺留分については、父母や祖父母のみが相続人になる場合は相続分の3分の1になるものの、それ以外の場合は相続分の2分の1になるという話がなされることがあります。
書籍やネットにおいても、このような「分かりやすい」説明がなされることは、しばしばあります。
確かに、多くの事例では、上記の考え方で、遺留分を計算することができます。
しかし、現実には、このような計算方法を行うと、落とし穴にはまってしまうことがあります。
例えば、次のような事例ではどうなるのでしょうか。
・ 相続人は、被相続人の配偶者、被相続人の兄弟姉妹である。
・ 被相続人の配偶者が、被相続人の兄弟姉妹に対し、遺留分侵害額請求を行う。
先程の話からすると、配偶者が遺留分侵害額請求を行う場合には、配偶者の遺留分は、配偶者の相続分の2分の1であるということになりそうです。
この場合、配偶者の相続分は4分の3ですので、配偶者の遺留分は8分の3であるとの計算を行ってしまうかもしれません。
しかし、正しい回答は、配偶者の遺留分は2分の1です。
これは、遺留分の合計が2分の1になるところ、兄弟姉妹には遺留分が存在しないため、配偶者が2分の1の遺留分のすべてを主張することができるようになるためです。
実際、上記と同様の相続関係で、法律の専門家であるはずの弁護士が、配偶者の遺留分を8分の3と計算し、訴訟を提起している事例を見たこともあります。
このように、遺留分の計算1つをとっても、専門家でも誤解してしまうような落とし穴が潜んでいるのです。
3 相続に詳しい専門家にご相談ください
このように、相続について、ネットや書籍で調べた知識だけに頼って解決しようとすることは危険であり、専門家に相談することが望まれる分野です。
無料相談であれば、専門家に相談する際の抵抗感も少ないと思います。
私たちも、相続についての無料相談をお受けしており、相続案件を集中的に扱っている専門家がご相談にのらせていただきます。
相続でお困りのことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
不動産評価に強い専門家に相談すべき理由
1 相続と不動産評価

相続の場面では、相続人全員で協議を行い、すべての相続財産について、誰がどの財産を取得するかを合意する必要があります。
このように相続人全員の合意が必要となるため、相続財産の分け方について、相続人の間で意見調整が必要になる場合があります。
相続財産に不動産が含まれている場合には、意見調整を行うにあたり、不動産の評価を行う必要が生じることがあります。
不動産の評価をおこなうべき場面は、具体的には、次のような場合です。
・不動産を特定の相続人が取得し、他の相続人に対して代償金を支払うこととする場合
・相続税の申告を行うにあたり、不動産の評価を行う必要がある場合
ところで、不動産の評価は、専門家によって、得手不得手が大きく異なってきます。
このため、専門家が行う主張次第で、評価結果が大きく異なることがあります。
不利な評価結果を用いることは避けたいところですので、不動産の評価が必要な場合には、不動産評価に強い専門家に相談し、妥当な評価を行ってもらうのが良いでしょう
以下では、専門家が行う主張によって評価額が大きく異なってくることについて、具体例を挙げて説明したいと思います。
2 無道路地の評価が問題となった例
この事例では、当初、固定資産評価額に基づいて、相続の話し合いが進められていました。
相談者は、相続財産である宅地の1つを、固定資産評価額どおりに評価し、その他の相続人に対して代償金を支払うこととなっていました。
ところが、その宅地は、固定資産税評価額では高い価額が付されていたものの、道路に接していませんでした。
道路に接していない土地は、通常、建物を建築することができませんので、なかなか買手がつかず、評価額が大きく値下がりすることが多くあります。
このことを考慮すると、固定資産評価額は、その土地の評価額としては過大であるように思えました。
そこで、周囲の土地の名義について調査したところ、相続財産である宅地と道路との間にある土地が、被相続人の親族の名義になっていることが判明しました。
さらに調査したところ、その宅地は、もともと、道路との間にある土地と一体の土地になっており、いずれも被相続人が所有していたものの、その後、道路との間にある土地が被相続人の親族に譲渡されたため、道路と接しない状態になったことが判明しました。
本来、道路との間にある土地が被相続人の親族に譲渡されたことにより、道路と接しない状態になったのであれば、その時点で、固定資産評価額の減額調整がなされるようにも思えます。
しかし実際には、その時点で減額調整がなされていませんでした。
このような事情から、問題の宅地は、道路に接している土地と同じ扱いがなされ、本来よりも過大な固定資産評価額が付されたままとなっていたのです。
このような事情が判明したため、問題の宅地については、固定資産評価額ではなく、実際の時価を算定すべきであるとの話になりました。
最終的には、不動産鑑定士による鑑定評価がなされ、鑑定結果に基づいて、相続についての話し合いが進められることとなりました。
3 不動産の相続についてのご相談
以上から、不動産の相続においては、不動産評価に強い専門家に相談するかどうかにより、大きく結果が異なってくる場合があります。
私たちは、不動産の評価が争われた案件も多く担当していますので、どのような方法で不動産の評価を行うか、不動産の評価額についてどのように主張すべきかに関して、お困りの点がありましたら、お気軽にご相談ください。
相続のご相談から解決までにかかる時間
1 相続のご相談から解決までの流れ

多くの方にとって、人生で相続の問題に直面する機会は、片手に満たない回数に限られるのではないかと思います。
このため、相続の問題がどのような流れで解決されるのかは、イメージがわきにくいのではないかと思います。
相続についてご相談いただいてから、解決に至るまでの流れは、おおむね以下のとおりです。
① 相続についての調査
② 相続人全員との話し合い
③ 相続財産の払戻し、名義変更の手続き
以下では、それぞれの段階について、おおまかな内容を説明し、相続問題の解決までに要する時間の目安を明らかにしたいと思います。
2 相続についての調査
相続についての調査では、相続人の調査と相続財産の調査が重要なポイントとなってきます。
相続人の調査では、相続関係を明らかにする戸籍をひと通り取得する必要があります。
例えば、相続人が、被相続人の配偶者、被相続人の子の場合ですと、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍、相続人の現在の戸籍を、漏らすことなく取得する必要があります。
ここで取得した戸籍は、後日の、相続財産の払戻し、名義変更の手続きでも用いることとなりますので、きちんと保管しておく必要があります。
必要な戸籍をすべて取得するのに必要な時間は、相続関係によって異なります。
一般に、相続人が子や父母のみである場合は、戸籍を取得するのに要する時間は短くて済み、目安は1~3週間になります。
一方で、相続人に兄弟姉妹や甥姪が含まれる場合は、より多くの戸籍を取得する必要がありますので、戸籍を取得する時間も、より多くかかります。
また、転籍など、戸籍の移動を繰り返している場合も、すべての戸籍を取得するのに多くの時間が必要になります。
当法人の相続人調査の業務内容のサポート内容については、こちらをご覧ください。
相続財産の調査では、不動産、預貯金、有価証券の有無、評価額などを調査します。
調査に要する時間の目安は1か月前後です。
ただし、財産についての情報が乏しく、不動産のある市町村、預貯金のある金融機関、有価証券のある証券会社が判明していない場合には、総当たり式で調査を行う必要があることもありますので、さらなる時間を要することとなります。
3 相続人全員との話し合い
相続人全員と話し合い、誰がどの財産を取得するかを決める必要もあります。
遺産を分割するための協議では、相続人全員が合意を行う必要がありますので、必ず、相続人全員で話し合いを行わなければなりません。
話し合いにどれだけの時間を要するかは、相続人同士の関係、各相続人の主張によって、ケースバイケースです。
数週間のうちに話し合いがまとまることもありますし、意見が対立して何か月も話し合いを続ける必要があることもあります。
法律上、複雑な争いがある場合には、1年以上の期間をかけて、協議が行われることもあり得ます。
4 相続財産の払戻し、名義変更の手続き
相続人全員との話し合いが終わった後は、話し合いの結果に基づいて遺産分割協議書を作成し、相続財産の払戻し、名義変更の手続きを行います。
相続財産の払戻し、名義変更に要する時間の目安は、おおむね1~2か月です。
ただし、不動産が存在する場所を管轄する法務局の数、金融機関や証券会社の数次第では、さらに時間を要することもあります。
相続について専門家に相談するべきタイミング
1 専門家に相談すべき場面

相続では、多種多様な問題が発生します。
このため、相続について専門家に相談すべき場面も様々であり、専門家に相談するべきタイミングも、ケースバイケースになってきます。
ここでは、専門家に相談するべき代表的な場面と相談すべきタイミングについてご説明したいと思います。
2 相続の手続きを行う場面
相続の手続きを行う場面では、専門家に相談を行うことがあります。
例えば、相続財産に不動産が含まれている場合は、相続登記の手続きが必要になります。
また、預貯金、株式、投資信託、公社債についても、相続の手続きを行わなければ、払戻や換金を行うことができません。
このような手続きを行うためには、どのような書類を作成し、どのような書類を準備すべきかについて、専門家への相談が必要になることがあります。
このような、相続の手続きを行う場面では、相続財産の分け方について、相続人の間でおおむねの意見がまとまった段階で、専門家に相談するのが良いでしょう。
なぜなら、相続財産の分け方次第では、どのような相続の手続きを行うかが変わってくる場合があるためです。
3 相続についての意見調整を行う場面
相続では、相続財産の分け方については、相続人全員が合意して決定する必要があります。
しかし、場合によっては、相続人同士の意見対立が激しくなり、相続財産の分け方について意見が一致しないことがあります。
このような場合には、相続人同士の意見を調整しなければ、その先の手続きを進めることができません。
このような場面では、意見の不一致が明らかになった段階で、専門家に相談するのが良いと考えられます。
なぜなら、専門家から、意見調整のためのヒントが得られることがあるためです。
また、この段階で専門家に依頼し、専門家を介して意見調整を行うことも考えられます。
ただし、特別受益、寄与分等の法的問題について意見対立がある場合は、もっと早い段階で専門家のアドバイスを得た方が良いことがあります。
これらの法的問題が相続財産の分け方にどう影響するかについて、早い段階で専門家の助言を得ることで、説得力のある話し合いを進めることが期待できるからです。
4 何らかの問題が生じたら相談する
このように、専門家に相談すべきタイミングは、問題となっている事項、相続人の意見、相続財産の内容等によって異なってきます。
実際には、相談すべきタイミングかどうか、判断に迷うことも多いと思いますので、何らかの問題が生じたら、あるいは生じそうであったら、一旦は専門家に相談してみるという考え方でも良いのではないかと思います。
この場合は、相談をお受けした専門家が、どの段階でどのような関与を行うのが望ましいのかも含めて、アドバイスいたします。
専門家による相続財産(不動産)の調査
1 不動産の調査の必要性

相続手続きを終えるためには、被相続人名義のすべての財産について、名義変更や払戻等を行う必要があります。
このように、被相続人名義のすべての財産について名義変更や払戻等の手続きを行うためには、相続財産の調査を漏れなく行うことが必要不可欠です。
ここでは、相続財産の中でも、不動産の調査方法について、いくつかの注意点を説明したいと思います。
2 共有の不動産に注意
不動産に関しては、毎年4月から5月に届く固定資産税納税通知書の課税明細書の部分を確認すれば、被相続人が所有していた不動産を網羅的に把握することができます。
ここで注意しなければならないのは、固定資産納税通知書は、被相続人が単独で所有している不動産と、被相続人が誰かと共有している不動産とで、別々に発行されるということです。
被相続人が単独で所有している不動産の固定資産税納税通知書を見逃すことはあまりないと思いますが、被相続人が誰かと共有している不動産の固定資産税納税通知書については見逃されることが多いので、注意が必要です。
特に、被相続人以外の人が共有資産代表者として届出がなされていると、固定資産税納税通知書の宛名書には、被相続人以外の人が表示され、被相続人が表示されないため、見逃しの原因になってしまいます。
さらに、共有資産代表者が被相続人とは別の住所に住んでいると、被相続人の住所には固定資産税納税通知書が届きすらしませんので、そもそも、共有不動産の存在に気づく機会もありません。
被相続人が誰かと共有している不動産を調査したい場合は、市町村役場(四日市市にある不動産の場合は四日市市役場)の資産税課に赴き、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を取得して調査することが考えられます。
参考リンク:四日市市・固定資産課税台帳 閲覧申請書(土地・家屋名寄帳)
窓口において、被相続人が誰かと共有している不動産も含めて、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)の発行を申請すると、共有不動産の名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)も取得することができます。
ただ、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を取得する場合も、窓口において、被相続人が所有する不動産という指定だけで発行を申請すると、被相続人が単独所有している不動産のものだけが発行されることがあります。
名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)の発行を申請する際には、被相続人が共有している不動産を含む、すべての不動産のものの発行を申請した方が良いでしょう。
3 1月1日以降の名義変更に注意
固定資産納税通知書や名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)に記載される不動産は、被相続人がその年の1月1日時点で所有していた不動産になります。
このため、これらの書類には、その年の1月1日以降の名義変更が反映されていません。
例えば、被相続人がその年の1月1日以降に不動産を取得した場合には、その不動産は新たに被相続人の財産に加わることになるので相続財産に含まれるのですが、固定資産税納税通知書には記載がないこととなります。
このような場合に、固定資産税納税通知書に基づいて相続手続きを行うと、被相続人が新たに取得した不動産を見逃してしまうことになってしまいます。
このような事態を避けるためにも、被相続人がその年の1月1日以降に不動産を買ったり売ったりしている場合には、特に注意する必要があります。
被相続人が直近で不動産を売買しているという情報がある場合には、売買契約書を確認し、売買契約書に記載されている不動産についても調査を行う必要があります。
売買契約書が確認できない場合には、不動産仲介業者に問合せを行う、不動産のおおむねの所在地を確認し、対応する登記簿を取得するといった作業も必要となってくるでしょう。
専門家に相談する際の流れ
1 専門家への相続の相談

相続について専門家に相談する場面は、そう多くないものと思いますので、専門家に相談する際の流れがどのようなものであるかは、イメージが湧きにくいかもしれません。
そこで、以下では、相続について、専門家に相談する場合のおおむねの流れを説明したいと思います。
2 ご相談前の準備
相談前の段階では、あらかじめ、どのような事項を相談するかをまとめておいた方が、相談時に聞きたいことを聞けず、結局疑問点が残ったままになってしまうような事態を避けることができます。
メモ書き程度のものでも構いませんので、あらかじめ、相談する事項をまとめてから、相談の日を迎えるのが良いでしょう。
また、相談前の段階では、親族関係や相続財産に関する情報を、あらかじめまとめておいた方が良いと思います。
相続では、相談の前提として必要となる情報が多く、これらの情報をきちんと伝えられるかどうかによって、結論も大きく異なってきます。
このような理由から、相談の際には、親族関係や相続財産に関する情報の確認を念入りに行うこととなりますが、一からこれらの情報を確認するとなると、それだけで多くの時間を使ってしまい、質問したいことを質問できずに終わってしまうといったことも起こりかねません。
また、万一、情報の説明漏れが生じると、専門家の回答が、本来とはまったく異なる回答になってしまうおそれもあります。
こうした事態を避けるためにも、あらかじめ、親族関係や相続財産に関する情報をまとめておいた方が良いです。
この点についても、メモ書き程度のものでも構わないと思います。
3 ご相談時の流れ
相談時の流れは、個々の専門家で異なってくるところがあります。
例えば、まずは、相談者から必要な情報、疑問に思っていることを伝えた上で、専門家が疑問点に回答するといった流れになることがあります。
他には、専門家が、相談者に対して、重要と考えるポイントを質問して一通りの情報を確認した上で、疑問点に回答するという流れになることもあります。
どちらの流れが良いかは、質問内容や質問される方によっても異なってきますので、当法人では、ご相談の際、最も適切と思われる流れで、ご相談をお受けしています。
4 ご相談後について
相談のみで問題点が解消した場合は、相談後に特に行うことはありませんが、その後も専門家に依頼することを希望される場合は、どのような事項を、どのような費用負担で専門家に依頼するかを話し合い、正式に委任契約を締結する流れになります。
各専門家が協力できることの強み
1 相続分野の特徴

相続分野は、様々な専門家が関与するため、各専門家が協力する必要性が高い分野です。
遺産分割について協議がまとまらない場合は、法的紛争の専門家として、弁護士が関与することがあります。
相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産の名義変更の専門家として、司法書士が関与することがあります。
相続税の課税価格が基礎控除額を越えるため、相続税が課税される場合には、税金の専門家として、税理士が関与することがあります。
特定遺贈で農地の名義変更を行う場合には、公的機関の許可申請の専門家として、行政書士が関与することもあります。
このように、相続では、複数の専門家が関与するべき場合があるため、専門家同士の緊密な連携が求められることがあります。
各専門家が緊密に連携することができれば、スムーズに問題の解決にあたることができます。
このことは、相続の分野では、大きな強みとなります。
逆に、連携が不十分だと、問題がなかなか解決しなくなってしまう可能性があります。
以下では、相続の問題を解決できなかった具体的な失敗例を説明し、それぞれの専門家が連携することの重要性を説明したいと思います。
2 連携が不十分な失敗例
この案件では、相続人間の対立が激しかったため、まずは、弁護士が相続人間の意見を調整し、その後、司法書士が不動産の名義変更を行うことを予定していました。
弁護士が相続人間の意見を調整した結果、ある相続人が不動産を取得し、他の相続人が預金を取得することとなりました。
そして、弁護士が遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印と印鑑証明書を得て、一通りの書類が揃うこととなりました。
この時点では、司法書士は、書類等の作成に関与していませんでした。
このようにして相続人間の協議がまとまったため、不動産を取得した相続人が司法書士に連絡を取り、不動産の名義変更を依頼することとなりました。
しかし、司法書士からは、作成済みの遺産分割協議書では名義変更することはできないとの回答がありました。
その理由は、以下のとおりでした。
司法書士が、登記簿で記録されている被相続人の住所を確認したところ、被相続人がかなり前に住んでいた住所が登録されたままとなっており、その後、被相続人が複数回引っ越しをしたにもかかわらず、住所変更が一度も行われていなかったことが判明しました。
この場合、登記簿上の所有者の住所と、被相続人の最後の住所が異なることとなりますので、一見すると、登記簿上の所有者と被相続人とが同一人物であるかどうかが分からないこととなります。
このようなときは、不動産を取得した相続人は、何らかの根拠に基づいて、登記簿上の所有者と被相続人とが同一人物であることを証明する必要があります。
除かれた戸籍の附票を取得することができれば、被相続人の住所変更の履歴を確認することができますが、除かれた戸籍の附票の保管期間が経過しているため、これを取得することができないことがあります。
また、対象となる不動産の権利証が残っていれば、手続が可能となることがありますが、権利証を紛失してしまっている場合には、他の方法を用いる必要があります。
このような場面では、遺産分割協議書とは別に、登記簿上の所有者と被相続人とが同一人物であることを記載した申述書を作成し、相続人全員の実印と3か月以内に発行された印鑑証明書を得る必要があります。
こうした書類が集まらなければ、不動産の名義変更を行うことができないこととなってしまいます。
この案件では、このことが発覚してから、他の相続人に、申述書に実印を押印することを求めましたが、他の相続人は、すでに問題なく預金の払戻ができていたためか、申述書への押印を拒否してきました。
このため、相続人間の協議が成立し、預金の手続が済んだものの、不動産だけが名義変更できないという事態が生じてしまいました。
3 各専門家が協力する必要性
先述の事態を避けるためには、弁護士と司法書士が連携して、どのような書類を作成すべきかを事前に協議しておくべきであったと言えます。
あらかじめ、弁護士が司法書士に必要書類を確認し、交渉時に遺産分割協議書だけでなく申述書への押印を得る行動をとっておけば、名義変更ができないといった事態が生じることは避けられたはずです。
このような例からも、相続分野では、各専門家が協力する必要性が大きいことが分かると思います。
相続の相談先を探される際は、専門家同士の協力体制が整っている事務所を選ばれることをおすすめします。
相続人の調査方法
1 相続人の調査の必要性

相続で、誰がどの財産を取得するかという協議を行う場合には、すべての相続人が協議に参加する必要があります。
そして、このような協議がまとまり、不動産や預貯金の相続手続きを行う段階においても、すべての相続人が書類作成に関与する必要があります。
このように、相続の場面では、すべての相続人が関わるため、相続人の調査が必要になるのです。
わずかな調査の漏れにより、後日、他に相続人が存在することが発覚するようなことがあると、協議や手続きを一からやり直す必要が生じてしまいますので、早い段階で相続人の調査を行い、相続人が誰であるのかを確定させる必要があります。
ここでは、相続人の調査の具体的な方法について、ご説明したいと思います。
2 相続人の調査方法
⑴ あらかじめ親族関係を聞いておく
相続人の調査にあたっては、あらかじめ、詳しい親族から、親族関係を聞いておくのが良いと思います。
このような情報を得ておくと、戸籍等の調査を行った際、調査漏れがあるかどうかを確認する重要な手がかりになります。
⑵ 被相続人の戸籍を取得する
相続人の調査自体は、市町村役場で戸籍を取得することによって行います。
どのような場合であっても、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する必要があります。
出生から死亡までの間に、改製(法改正等によって戸籍を作り直すこと)があった場合には、必ず、改製前の戸籍も改製後の戸籍も取得しなければなりません。
また、出生から死亡までの間に、転籍(本籍地の移動)があった場合には、転籍前の戸籍も転籍後の戸籍も必要になります。
結婚や離婚等の身分関係の変動があった場合も同様です。
⑶ 本籍地の変更があった場合
被相続人の本籍地の変更があると、複数の市町村役場で戸籍を取得する必要も出てきます。
このため、戸籍の記載内容を精査し、その前の本籍地がどこにあったかを確認し、その前の本籍地の市町村役場で古い戸籍を取得するといった作業も必要になってきます。
本籍地の変更が何回もなされていると、いくつもの市町村役場で戸籍を取得しなければならなくなります。
ただし、広域交付制度を用いて戸籍を請求できる場合には、本籍地と関係なく、どの市町村役場でもまとめて請求することができます。
⑷ その他に必要となる戸籍
被相続人の戸籍以外にどのような戸籍が必要になるかは、相続関係によって異なってきます。
例えば、被相続人の子のみが相続人になる場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて、相続人の現在の戸籍を取得すれば十分です。
これに対して、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、さらに、被相続人の父母の最後の戸籍、被相続人の兄弟姉妹の現在の戸籍も必要になります。
3 相続人の調査の依頼
このように、相続人の調査は、複数の市町村役場で戸籍を取得する必要があります。
また、戸籍の内容を精査し、漏れなく、確実に、戸籍を取得しなければなりません。
戸籍は普段あまり目にする機会がなく、見慣れていないという方が多いかと思います。
見慣れない資料の中身を読み解くという点でも、負担が大きいと感じられるかもしれません。
そのような場合は、相続を得意としている専門家にご相談ください。
私たちは、相続人の調査はもちろん、その後の相続手続き等もサポートできる体制を整えております。
相続でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
専門家による相続財産(金融資産)の調査
1 金融資産の調査の難しさ

普段の生活の中では、ご自身がどのような財産を有しているかについて、誰かに話すことはほとんどないかと思います。
親子等の近い親族であっても、財産の内容についての詳細な情報を伝え合っていることは、少ないのではないでしょうか。
このため、他の人が財産の内容についての詳細な情報を得ることがないまま、相続の場面を迎えることとなってしまうことは多いのが現実です。
実際、相続人が、被相続人が有している預貯金や株式、投資信託、債券について、正確に把握できていないことが多く、相続の手続を行う前提として、相続財産の調査を行う必要が生じてくることが多いです。
ここでは、被相続人が有していた金融資産について、専門家がどのような調査を行うか説明したいと思います。
専門家に依頼するとどのような財産調査をしてくれるのか知りたいという方はご覧ください。
2 預貯金の調査
預貯金については、被相続人の自宅に残された通帳、証書が手がかりとなることが多いです。
通帳、証書が残されていると、その銀行、支店に預貯金口座が存在する可能性が高いからです。
このような手掛かりがあれば、通帳、証書が残されている銀行、支店に問い合わせを行い、口座の有無や残高を確認することができます。
銀行、支店に問い合わせを行う際には、その銀行、支店に複数の口座が存在する可能性がありますので、すべての口座の有無、残高を確認します。
同じ銀行の別の支店に口座が存在する可能性もありますので、合わせて、全店照会を行い、別の支店の口座の有無も確認するとスムーズかと思います。
また、近年では、銀行を通して投資信託や債券の取引が行われていることがありますので、投資信託や債券についても、調査の対象とした方が良いです。
現実には、通帳、証書が見つからず、銀行、支店が特定できないことがあります。
単に、被相続人が通帳、証書を紛失してしまっている場合もあるでしょうし、ある相続人が通帳、証書を保管しているのに、他の相続人に対しては通帳、証書が存在するという情報を伝えない場合もあるでしょう。
また、近年では、ペーパーレス化を推奨している銀行も存在するため、通帳、証書が発行されていないこともあります。
このように手掛かりがない場合には、被相続人の住所の近辺の銀行、支店を総当たりで調査することも検討します。
3 株式、投資信託、債券の調査
株式、投資信託、債券については、証券会社から被相続人の自宅に定期的に届く、取引残高報告書により、取引のある証券会社や銀行、支店を特定することができます。
また、取引残高報告書を確認すれば、株式、投資信託、債券の残高を確認することもできます。
株式、投資信託、債券についても、預貯金と同様の理由から、証券会社や銀行、支店を特定する手掛かりを得られないことがあります。
このような場合には、証券保管振替機構の登録済加入者情報の開示請求を用いることを検討します。
登録済加入者情報の開示請求を用いれば、日本全国の証券会社や銀行の中から、被相続人が有価証券の取引を行っていた証券会社や銀行がどこであるかを網羅的に調べることができます。
被相続人が取引を行っていた証券会社、銀行が特定できれば、その証券会社、銀行に問い合わせを行い、株式、投資信託、債券の残高を調査します。
相続は誰に依頼をするべきか
1 相続を依頼する専門家の選び方

相続問題を専門家に依頼する場合には、専門家選びが重要になってきます。
相続の問題は、様々な特色があり、それを踏まえて依頼する専門家を選ばなければ、相続問題を解決できなかったり、不利な内容での解決になってしまったりするおそれがあります。
ここでは、相続について依頼する専門家を選ぶためのポイントを、いくつか説明したいと思います。
2 相続に関係する知識を網羅的に把握している専門家を選ぶ
⑴ 専門家はそれぞれ異なる役割を持っている
相続に関係する専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等、様々です。
これらの専門家は、それぞれ、異なる役割を持っています。
例えば、相続人の間で、どのように相続するかについての意見が一致せず、意見を調整しなければならないような場面では、弁護士が関与することとなります。
また、相続財産の額が一定額を超えており、相続税の申告や納付が必要になった場合には、税理士が関与することとなります。
⑵ 他の専門家の役割に詳しいとは限らない
このように、相続に関係する専門家の種類は様々ですが、多くの場合、それぞれの専門家は、他の専門家がどのようなことを行っているかについて、詳細かつ正確な知識を持っているわけではありません。
このため、特定の専門家が自分の持っている知識に基づいて対処したところ、他の専門家にとってはその対処が適切ではなかったということが起きかねないのです。
例えば、弁護士が、相続人同士の意見を踏まえて遺産分割協議書を作成したものの、その分割方法だと、相続税の税額軽減の制度を用いることができなくなり、相続税の計算上不利になるといったことも起こり得ます。
⑶ 網羅的な知識を把握している専門家に相談を
以上から、相続では、自分以外の専門家の知識も含めて、網羅的な知識を把握しているか、異なる専門家同士が連携できる体制を整えているかのいずれかの条件を満たす専門家に依頼することが望ましいといえます。
3 相続に関する最新の詳しい知識を持っている専門家を選ぶ
相続では、事案ごとの些細な違いにより、どのような対処をすべきか、どのような書類を作成すべきかが大きく変わってくることがあります。
例を挙げると、不動産の登記簿上に記載されている被相続人の住所が、亡くなった時と同じ住所である場合と、古い住所のままになっている場合があります。
古い住所のままになっている場合には、相続登記を行うため、追加の書類が必要になってきます。
相続では、以上のような事案ごとの些細な違いを見逃すことなく、その違いを踏まえてどのような対処を行うべきか、詳細な知識を把握している必要があります。
また、相続では、様々な分野で、法令や先例の変更がなされています。
例えば、相続税については、毎年のように、課税のルールの変更が行われています。
他にも、どのような書類が存在すれば不動産の登記申請ができるかについて、法務局の取り扱いが変更されることも、しばしばあります。
相続の場面では、このような実務の変更に対応するためにも、常に最新の知識をもつようにしておく必要があります。
4 相続を得意とする専門家に相談する
このように、相続の場面では、網羅的な知識を用いることができる専門家、詳細かつ最新の知識を持っている専門家に依頼することが重要です。
この点を踏まえると、相続に特化した専門家に相談するのが、より適切な解決を行う上での近道になると言うことができます。
専門家による相続の調査
1 相続の場面で必要な調査

被相続人が亡くなると、残された相続人で共同して、相続の手続きを行う必要があります。
相続の手続きを行うにあたっては、あらかじめ、一通りの調査を行い、手続きに漏れが生じないようにした方が望ましいです。
このような調査を十分にしないまま相続の手続きを進めてしまうと、後日、想定外の事実が判明し、最悪の場合、相続の手続きを最初からやり直さなければならなくなることもあります。
相続で必要な調査としては、代表的なものとしては、以下のものを挙げることができます。
・ 遺言の調査
・ 相続財産の調査
・ 相続人の調査
ここでは、それぞれについて、具体的にどのような調査を行う必要があるのかを説明したいと思います。
2 遺言の調査
遺言の調査については、意外と行われていないことが多いです。
そのため、当初、遺言がないという前提で遺産分割協議を進めたものの、後になって遺言の存在が判明する事態がしばしば生じています。
遺言の存在が後で明らかになると、基本的には、それまでに行った協議が意味を失ってしまい、最初から相続の手続き等をやり直すこととなってしまいます。
このように、遺言の有無の影響力は極めて大きいため、相続では、まずは遺言の有無を調査することが重要になってきます。
以上を踏まえると、まずは、遺言があるかどうかを確認することが重要であることが分かります。
自筆の遺言でしたら、自宅の重要書類が保管されている場所や、銀行の貸金庫、四日市支局等お近くの法務局(遺言書保管所)等を確認することになります。
参考リンク:法務省・07 管轄/遺言書保管所一覧
公正証書による遺言でしたら、四日市公証人合同役場等、お近くの公証役場で、遺言の検索を行うこととなります。
参考リンク:日本公証人連合会・公証役場一覧
3 相続財産の調査
正確な相続財産を確認できなければ、どのような相続手続きを行うべきか判断することが難しくなります。
そのため、相続手続きに取りかかる前には、相続財産調査をしっかりと行う必要があります。
多くの場合、父母が普段利用している銀行くらいは分かるかもしれませんが、何銀行の何支店に口座があるかを網羅的に把握できていることは少ないかもしれません。
不動産についても、自宅以外に田畑や山林を所有している場合には、生前の段階から、どこのどの範囲の不動産を所有しているかを正確に把握できていないこともあるかと思います。
生命保険についても、証書を発見しない限り、どの保険会社にどのような保険契約があるかを把握することができないことが多いのではないでしょうか。
相続の場面では、このような財産を把握するために、被相続人の自宅に残されていた通帳、権利証、証書等の書類や、自宅に届く手紙、相続人の断片的な記憶等から、相続財産の調査に着手しなければならないことが、しばしばあります。
4 相続人の調査
相続の手続きは、相続人全員が関与して行う必要があります。
相続人の一部が漏れた状態で手続きを進めようとしても、手続きを完了することはできません。
そのため、相続人調査を行い、誰が相続人になるのかを確定することは、相続の手続きを進める上で不可欠の前提になります。
相続人が誰であるかは自明のことと思われるかもしれません。
ところが、現実には、相続人の調査を行った結果、初めて、把握していなかった相続人の存在が判明することがあります。
例えば、被相続人に知られていなかった子がいることが判明するといったことは、現実に起こり得ます。
また、連絡がとれない親族がいる場合、相続関係が判然としないことが起こり得る可能性が高いです。
相続人調査を行う際には、少なくとも、被相続人の出生から亡くなるまでのすべての戸籍を取得する必要があります。
このような戸籍を取得することによって、相続人が誰かが客観的な資料で確定されることとなります。
相続した不動産の登記のための必要書類
1 登記申請の必要性

相続人同士の話し合いが成立し、どの不動産を誰が相続するかが決定したとしても、自動的に、登記上の名義人が被相続人から相続人に変更されるわけではありません。
登記上の名義人を変更するためには、不動産を取得した人が申請を行う必要があります。
ここでは、遺産分割が成立した場合に、相続した不動産の登記申請にあたって、どのような書類が必要になるかについて、説明を行いたいと思います。
2 戸籍、住民票関係の書類
どのような場合でも共通して必要になる書類は、以下のとおりです。
⑴ 相続人を特定する戸籍
相続人を特定する戸籍として、どのようなものが必要になるかは、相続関係によって異なります。
例えば、相続人が配偶者と子である場合や、相続人が子のみである場合には、被相続人に何名の子がいるかを特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて揃える必要があります。
⑵ 相続人全員の現在の戸籍
遺産分割協議の時点で、相続人全員が存命であることを確認するために必要になります。
⑶ 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
戸籍に記載されている被相続人と、登記上の名義人とが、同一人物であることを確認するために必要になります。
住民票の除票や戸籍の附票に記載されている住所と登記上の住所が一致するかどうかによって、両者が同一人物であるかどうかが判断されます。
⑷ 不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票
不動産を取得した相続人の住所を確認し、新たな名義人の登記上の住所をどこと記載すべきかを確認するため、必要になります。
3 その他の必要書類
上記の書類以外には、遺産分割の成立を証明するための書類が必要になります。
どのような書類が必要になるかは、遺産分割の成立の仕方によって異なります。
例えば、遺産分割協議書に基づいて名義変更を行う場合は、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
加えて、不動産の評価証明書が必要になります。
これは、登記申請の際に課税される登録免許税を算定するために必要になります。
相続に関するお役立ち情報
当サイトでは、相続の問題にお悩みの方に向けて、様々な情報を紹介しています。お役立ち情報やQ&Aなどもあわせてご覧ください。