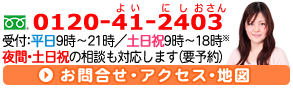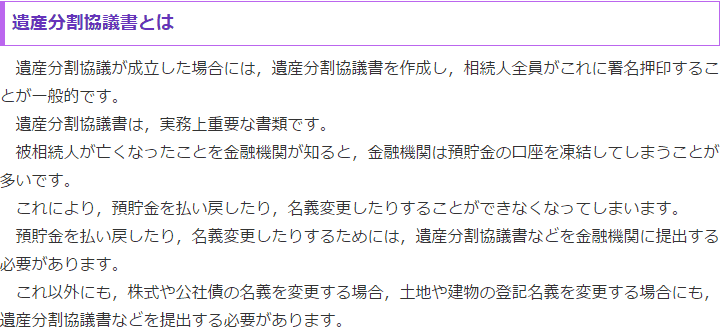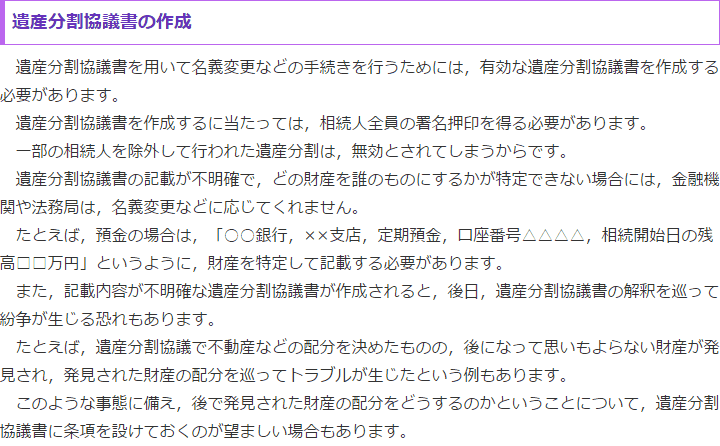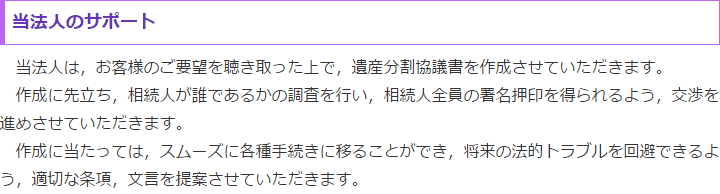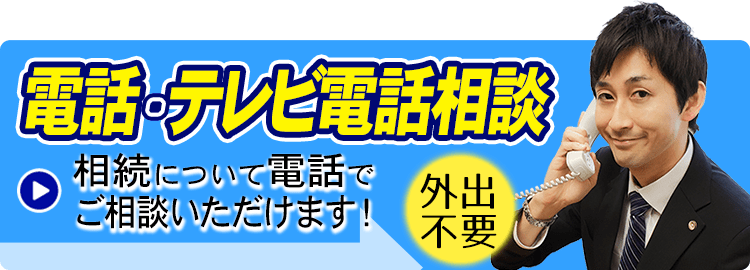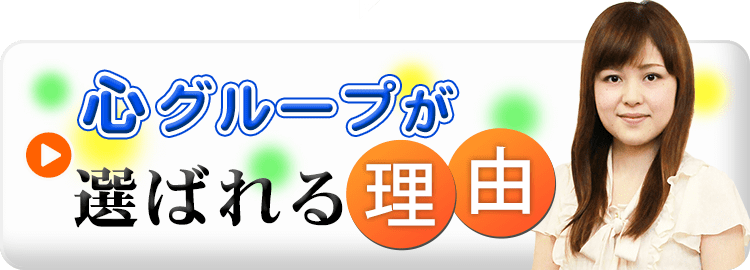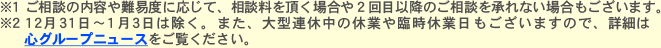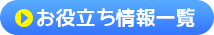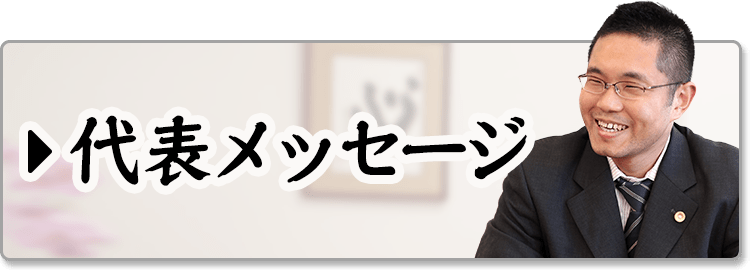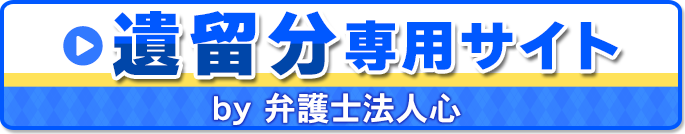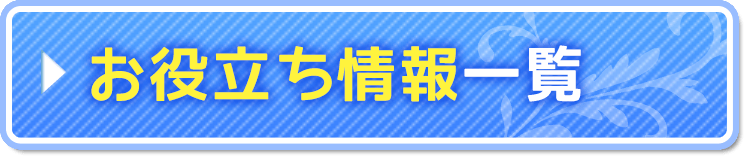遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成において注意すること
1 遺産分割協議書の持つ意味

遺産分割協議書は、相続人の誰がどのような相続財産を取得するかについて、相続人全員が合意した内容を取り決めた書類になります。
遺産分割協議書では、「●●の土地は●●が取得する」というように、個々の財産について取得者を取り決めるか、「●●はすべての相続財産を取得する」というように、包括的に取得者を取り決めるかのいずれかにより、取得する人を確定することとなります。
この協議書には、合意内容を明確にし、後日、相続人同士で争いが起きることを避ける意味があります。
口頭で決めただけだと「言った・言わない」の話になるおそれがありますし、そもそも、遺産分割についての合意が正式には成立していないと評価されてしまうおそれもあります。
遺産分割という重要な意思決定を行う以上、合意内容は書面で明確にしておくべきです。
遺産分割協議書には、もう1つ、重要な役割があります。
それは、遺産分割協議書で相続財産を取得する人を決めておくことにより、相続人全員の協力を得なくても、単独で払戻しや名義変更の手続きを行うことができるということです。
遺産分割協議書を作成しさえすれば、その後の手続きはかなりスムーズに進むこととなります。
ただ、遺産分割協議書を用いて単独で手続きを進めることができるようにするためには、いくつかの注意点があります。
ここでは、遺産分割協議書の作成の注意点について、ご説明したいと思います。
2 被相続人を特定することができる記載を設けること
遺産分割協議書では、誰の相続についての協議書であるかを明確に記載しておく必要があります。
それが確認できなければ、金融機関や証券会社等が把握している人物と、遺産分割の対象とされた被相続人とが同一人物であるか分からないため、手続きを進めることができなくなってしまうからです。
一般的には、被相続人の氏名、死亡年月日、最後の住所を記載して、誰の相続についての遺産分割協議書であるのかを明確にすることが多いです。
これに加えて、生年月日や本籍を記載することもあります。
逆にいえば、被相続人の氏名、死亡年月日、最後の住所が欠けていたり、誤記があったりすると、手続きを進めることができない可能性が生じてしまいますので、注意が必要です。
3 財産については、個別に正確に記載するか、包括的に記載すること
遺産分割協議書を用いて払戻しや名義変更の手続きを進めることができるようにするためには、特定の財産を取得したことがしっかりと分かるよう記載しておく必要があります。
遺産分割協議書の記載自体に不備があると、相続人同士の心の中では合意が成立しているとしても、払戻しや名義変更の手続きを進めることができません。
特に、財産は正確に記載する必要があります。
例えば、不動産の地番に誤記があったり、預貯金の口座番号に誤記があったりすると、誤記があった財産については手続きを進めることができないリスクが生じます。
こうした事態を避けるには、個別の財産を記載するのであれば、細心の注意を払って正確な記載を行う必要があります。
あるいは、「●●は●●銀行●●支店のすべての金融資産を取得する」というように、包括的な記載を行うことにより、こうしたリスクを回避することも考えられます。
4 相続人全員の実印が押印されていること
遺産分割協議書には、相続人全員の実印が押印されている必要があります。
実印以外で遺産分割協議書を作成しても、相続人間では遺産分割協議が有効に成立したと考えられるものの、単独で払戻しや名義変更の手続きを進めることはできなくなります。
また、実印を押印してもらったものの、印影がかすれていると、金融機関や証券会社の側で、本当に実印が押印されているかどうかを確認することができません。
単独で手続きを進めることができるようにするためには、遺産分割協議書には、相続人全員に鮮明に実印を押印してもらう必要があります。
5 相続人全員の印鑑証明書を添付する
遺産分割協議書に押印されているのが実印であることを確認できるようにするため、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書が添付されていないと、相続人間では遺産分割協議が有効に成立したと考えられるとしても、やはり、単独で払戻しや名義変更の手続きを進めることはできないこととなってしまいます。
印鑑証明書には、手続きの対象となる機関ごとに、有効期限が設定されています。
不動産の名義変更を行う場合は、法務局で手続きを行うこととなりますが、この場合は、基本的には、印鑑証明書の有効期限はありません。
相続後に発行されたものであれば、何年前の印鑑証明書であっても、手続きに用いることができます。
一方で、預貯金や株式等の名義変更を行う場合には、金融機関や証券会社等は、基本的には、3か月または6か月の有効期限を設けています。
このため、預貯金や株式等の手続きを行う場合には、印鑑証明書の有効期限内に、手続きを進める必要があります。
なお、印鑑証明書は、印鑑登録をしている土地の市区町村役場や、お近くのコンビニで取得することができます。
参考リンク:四日市市・印鑑登録証明書の交付申請