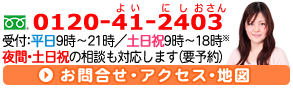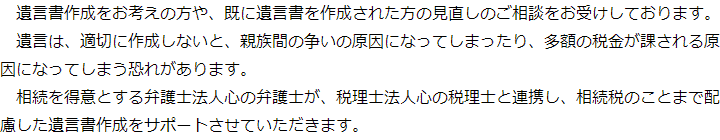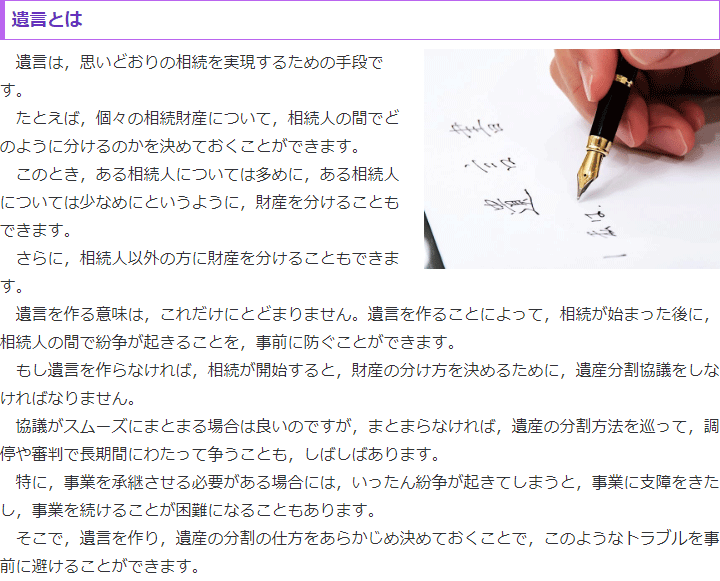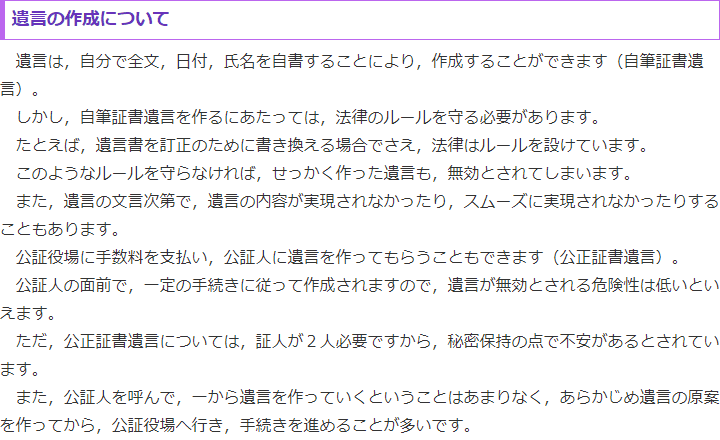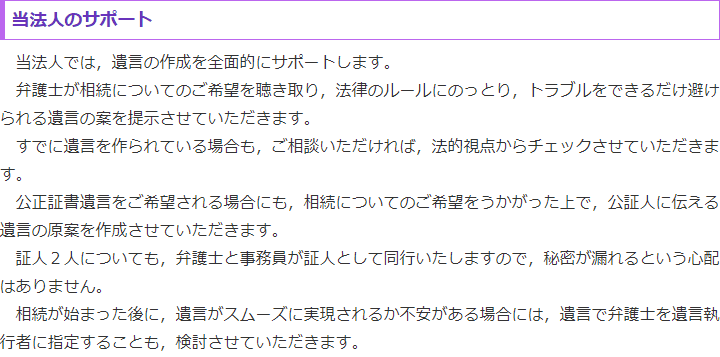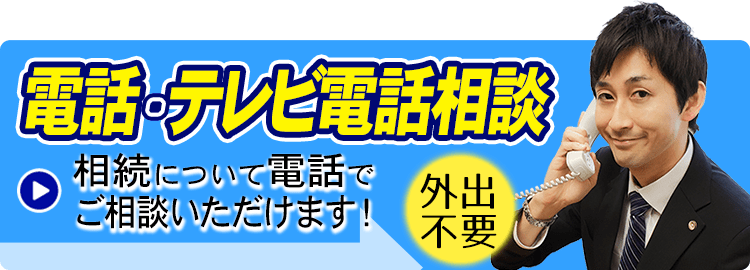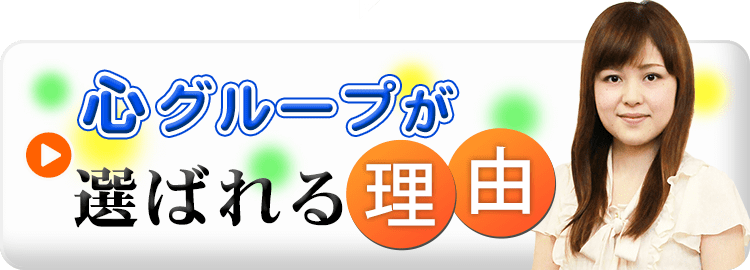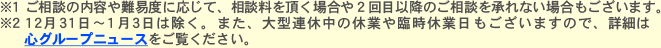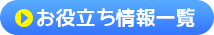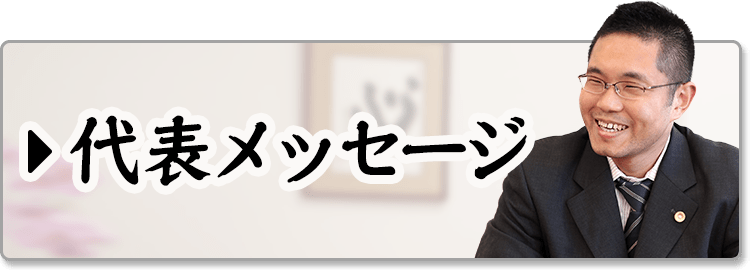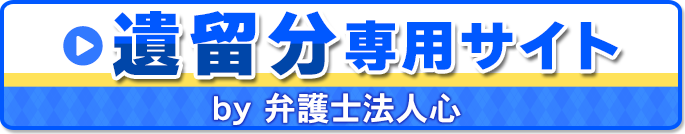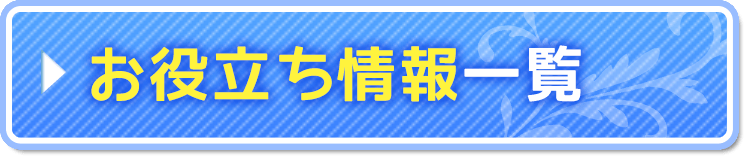遺言
相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント
1 遺言で揉める原因

遺言を作成すると、あらかじめ、誰がどの財産を取得するかを決めておくことができ、相続をめぐる紛争を避けることができるという話がなされることがあります。
ところが、現実には、遺言があるにもかかわらず、相続をめぐる紛争が発生してしまうということがあります。
遺言を作ったのに、その遺言書が原因でかえって紛争が発生してしまうとなると、遺言を作成する意味自体が失われてしまいかねません。
ここでは、どのような場合に、遺言を作成したにもかかわらず、紛争が発生してしまうかを説明するとともに、どのようにすれば紛争を回避できるのかについても説明したいと思います。
2 遺言の有効性を巡る争い
まず、特に自筆証書遺言について、遺言者自身が作成したものではないのではないか、偽造されたものではないかという理由から、争いが生じることがあります。
遺言には、作成者の氏名の記載、押印があるものの、遺言自体からは、実際には誰が筆記しているのかを確認する術はありません。
筆跡鑑定を行えば、誰の筆跡かを確定できるという話がなされることもありますが、筆跡鑑定を行うだけでも何十万単位の費用を要しますし、鑑定人により結論が分かれることもあるため、なかなか、筆跡鑑定を行っただけでは、紛争を解決できないことが多いです。
このように、特に自筆証書遺言については、誰が作成したものであるかを明確にしておく必要が大きいです。
こうした争いを回避するためには、遺言を作成する際の動画や写真を残しておく等の対策が考えられます。
また、遺言に押印するのは、実印の方が望ましいでしょう。
ただ、遺言者の死後には、印鑑証明書を取得することはできなくなってしまいます。
実印であることが確認できるよう、生前に印鑑証明書を取得しておき、遺言に添付しておくべき場合もあります。
3 遺留分を巡る争い
次に、遺言で特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるものとした場合には、その他の相続人から遺留分侵害額請求がなされることがあります。
遺留分は、一定の相続人に最低限保証された相続の権利であるため、遺言が作成されていたとしても、主張することができます。
この紛争を回避する対策としては、絶対的なものはありませんが、以下のようなものが考えられます。
第一に、特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるものとした動機を明確にしておくことが考えられます。
遺留分の請求がなされる原因の1つは、特定の相続人が相続財産の大部分を取得することについて、他の相続人が納得できないと主張することにあります。
遺言者自身の言葉で、特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるべき動機が明らかにされれば、他の相続人の理解が得られ、請求がなされないこともあり得ます。
また、ある相続人に対して十分な生前贈与がなされていることを動機として、他の相続人に相続財産の大部分を相続させるとの遺言が作成された場合は、特別受益の存在を理由として、ある相続人の遺留分侵害額請求が法律上認められないこともあります。
このように、遺言を作成した動機を説明したい場合は、遺言の付言事項に記載しておくことが考えられます。
第二に、他の相続人から遺留分の請求がなされることを想定して、それに相当する金銭の準備ができるようにしておくということです。
たとえば、遺言により、遺留分に相当する金銭も相続させるものとしておくことが考えられます。
遺言以外でも、死亡保険金により、それに相当する金銭を取得できるようにしておくことも考えられます。
死亡保険金は、原則、遺留分の算定の基礎となる財産には含まれませんので、死亡保険金も用いることにより、効果的に対策を行うことができます。
遺言でできること
1 遺言でできること

遺言でできることとして、相続分の指定、遺産分割方法の指定、財産の遺贈、遺言執行者の指定等が挙げられます。
これらの事項について、順次、定義を述べていけば、遺言でできることを明らかにすることができるとは思います。
とはいえ、これらの事項の定義だけを把握していても、遺言を有効活用することは難しいと思います。
これらの事項を遺言で定めた結果として、定めなかった場合と比較して、どのようなことができるようになるのかを把握していなければ、遺言を有効活用することはできないと思います。
ここでは、代表的な遺言事項について、遺言特有の効果として、どのようなことができるようになるのかを説明し、遺言を有効活用すべき場面を明らかにしていきたいと思います。
2 相続分の指定
遺言では、相続分の指定を行うことができます。
相続分の指定により、各相続人が相続すべき割合を決めておくことができます。
前提として、遺言がない場合であっても、相続人全員が合意すれば、各相続人が相続すべき割合を自由に決めることができます。
とはいえ、相続人に意見対立があり、相続人全員の合意が困難である場合には、各相続人が相続すべき割合は、基本的には、法定相続分で決まってしまいます。
また、相続人に熾烈な意見対立がなかったとしても、話し合いでは、法定相続分を参照して、各相続人が取得すべき割合を決めることも多いです。
このように、法定相続分は、相続人全員の合意が困難である場合や、相続人間で話し合いが行われる場合において、各相続人が取得すべき割合を決めてしまう、かなり強力なルールになります。
法定相続分だと、配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1で固定となり、それ以上の法定相続分を主張することはできません。
子が複数いる場合、子の法定相続分は均等になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、兄弟姉妹は4分の1の法定相続分を主張できます。
このような結論は、個別具体の事情によっては、受け入れ難いと思われることもあるでしょう。
しかし、法定相続分のルールに従えば、各自の取得分は、上記の結論で定まってしまうこととなります。
このような話をすると、特別受益(特定の相続人が生前贈与を受けているため、その相続人の相続分を減じるべきとの主張)、寄与分(特定の相続人が被相続人の療養看護や財産形成に貢献したため、その相続人の相続分を増加させるべきであるとの主張)を主張すれば、法定相続分を修正することができると考える方もいらっしゃるかもしれません。
確かに、特別受益、寄与分の主張を行うことにより、法定相続分を増減できる場合もあります。
しかし、特別受益、寄与分については、根拠となる事実を証明できるかどうかがネックになることが多いです。
また、特に寄与分については顕著ですが、根拠となる事実が証明できたとしても、増減される相続分がごく僅かであることも多いです。
このため、特別受益、寄与分の制度を前提としても、各相続人の取得割合は、法定相続分で杓子定規に決まってしまうことが多いと言うことができるのです。
こうした状況を打開し、各相続人が相続すべき割合を合理的に調整するためには、やはり、遺言により、あらかじめ相続分を指定しておくことが、必要不可欠であると言うことができます。
遺言により相続分を指定しておけば、たとえば、配偶者の相続分を2分の1超としたり、複数の子の相続分に差を設けたり、兄弟姉妹には相続させないものとする等、自由に各相続人が相続すべき割合を増減することができます。
後日、一部の相続人が遺言で定められた相続分に納得しなかったとしても、遺言の定めには拘束力がありますので、遺言の定めに基づき、各相続人が相続すべき割合を決めてしまうことができます。
ただし、配偶者と子が相続人になる場合、配偶者と父母が相続人になる場合については、各相続人について指定された相続分に特に顕著な差がある場合は、遺留分の主張がなされることがあります。
3 遺産分割方法の指定
遺言では、遺産分割方法の指定を行うこともできます。
遺産分割方法の指定により、個々の財産について、誰に相続させるかを決めておくことができます。
法律や遺言により相続分が定まり、各相続人が相続すべき割合が定まっていたとしても、各自の相続分によって誰が個々のどの財産を取得するかが定まらなければ、現実に個々の財産を引き継ぐことはできません。
誰が個々のどの財産を取得するかについても、相続人全員の合意によって決める必要があります。
誰が個々のどの財産を取得するかが定まらない限り、亡くなられた方の不動産を名義変更することはできませんし、預貯金の払戻や有価証券の売却を行うこともできません。
不動産の名義変更ができないと、不動産の賃借人が賃料の支払を拒んでくることがあり、不動産から発生する賃料を受け取ることができないといった問題が発生することもあります。
いわば、相続財産が宙に浮いてしまい、手をつけることができない状態が続いてしまうのです。
相続人間の意見対立が激しく、誰が個々のどの財産を取得するかを決定することができない場合は、このような相続財産が宙に浮いた状態がいつまでも続いてしまうこととなります。
また、相続人の一部がまったく連絡を取ることができない場合や、認知症に罹患している場合等、そもそも話し合いをすることが不可能な状態になってしまいます。
このように、相続財産が宙に浮いた状態が続いてしまうことを避けるためにも、あらかじめ、遺言で遺産分割方法の指定を行い、誰が個々のどの財産を取得するかを決めておくことが有益であると考えられます。
相続人間の交渉ができない、話し合いが紛糾してしまう等の状況が生じてしまうと、遺産分割を成立させるため、長期かつ複雑な手続を取らなければならなくなってしまいますので、万一の場合に備え、遺言を作成しておいた方が良いことがあります。
4 財産の遺贈
遺言を利用すれば、財産の遺贈を行うことができます。
遺贈は、自身が有している財産について、遺言によって、その一部または全部を譲渡することを言います。
遺贈により、相続人に対して財産を譲渡することもできますし、相続人ではない人に対して財産を譲渡することもできます。
ただ、相続人に対して財産を譲渡すること自体は、先述の遺産分割方法の指定によっても行うことができます。
遺贈が独自の力を発揮するのは、相続人ではない人に対して財産を譲渡する場合です。
遺言が存在しない場合は、相続財産は、基本的には、相続人しか引き継ぐことができません。
一旦、相続人が相続財産を引き継ぎ、その後、相続人ではない人に対して相続した財産を譲渡する方法を用いれば、最終的には、相続人ではない人に対して相続財産を引き継ぐこともできないわけではありません。
しかし、相続人に協力してもらうことができない場合は、このような方法を用いることはできません。
また、この方法だと、相続人から相続人ではない人に対して贈与がなされたものと扱われてしまいますので、多額の贈与税が課税されるおそれもあります。
相続人を介することなく、ご自身から相続人ではない人に対して直接相続財産を引き継ぐこととしたい場合は、遺言を作成し、財産を遺贈することが必要になってきます。
遺言により財産を遺贈すれば、相続人の協力を得られなくても相続人ではない人に財産を引き継ぐことができますし、これにより贈与税が課税されることもないこととなります。
このように、相続人ではない人に対して相続財産を引き継ぐことができるようになる点は、遺言独自のメリットであるということができます。
内縁の妻、事実上の養子、生前に世話になった人等、相続人ではない人に対して財産を引き継ぐ際には、遺言を有効活用する必要があることとなります。