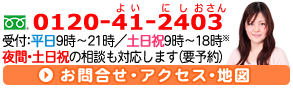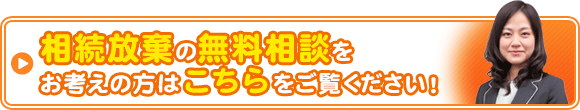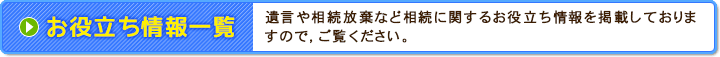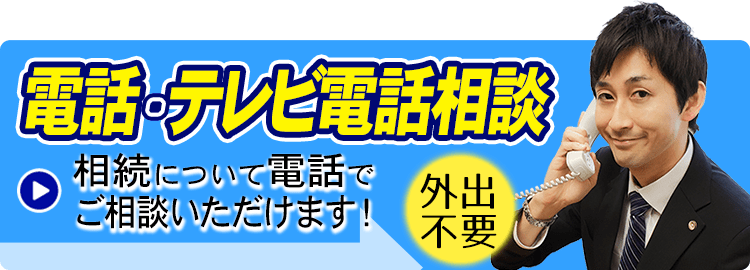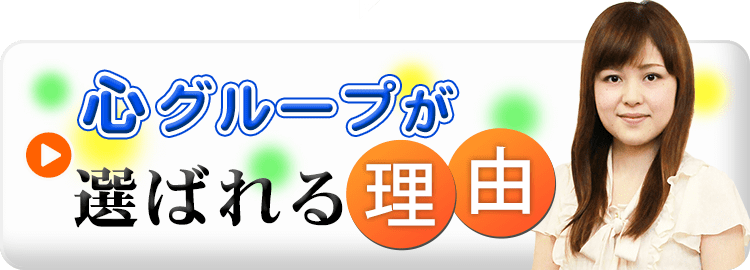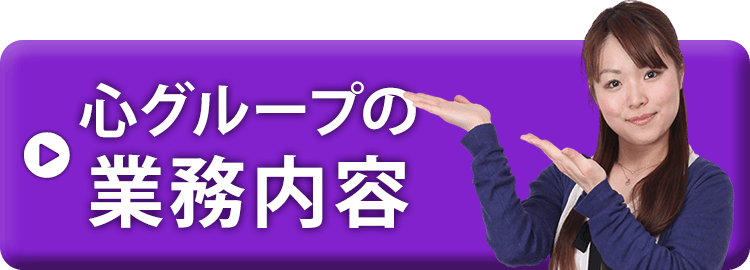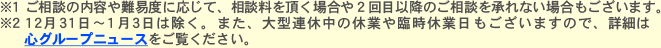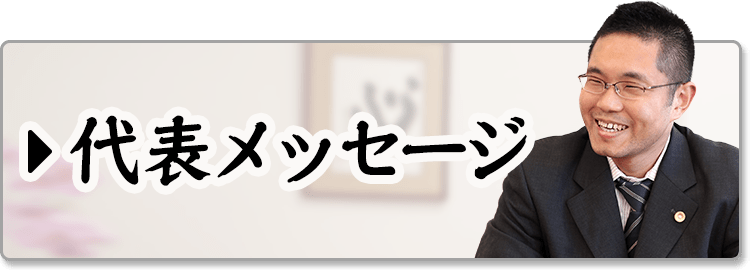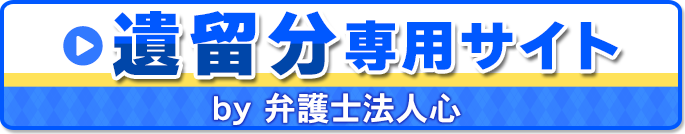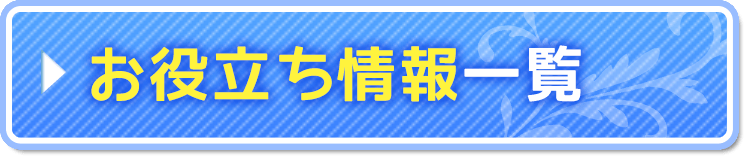相続放棄がなされた場合、残りの相続人はどうすればよいのでしょうか?
1 相続放棄
相続が発生した場合に、誰が法定相続人になるかは、法律で定められています。
例えば、被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が法定相続人になります。
一方、法定相続人に該当する人は、実際に、単純承認をして相続するという選択を行うか、相続放棄をして相続しないという選択を行うかを選ぶことができます。
相続放棄を行えば、最初から相続人ではなかったこととなりますので、相続放棄をした人は、相続には関与しないこととなります。
それでは、相続放棄をした人がいる場合、残りの相続人は不動産や預貯金の相続の手続きをどのようにして行えば良いのでしょうか?
以下では、そうなったときの手続き方法について、場合分けをして説明したいと思います。
2 残された相続人が1人である場合
相続放棄が行われたことにより、残された相続人が1人になることがあります。
例えば、相続人が配偶者と子1人である場合に、配偶者が相続放棄を行うと、残された相続人は子1人のみとなります。
この場合、遺産を取得する人は、1人しかいないこととなります。
したがって、相続放棄が行われたことをきちんと証明すれば、不動産や預貯金の相続手続きを行うことが可能になります。
そこで、このような場合には、残された相続人以外の人についての、相続放棄申述受理証明書を提出すれば、不動産や預貯金の相続手続きを進めることができることとなります。
相続放棄申述受理証明書は、共同相続人であれば、家庭裁判所(四日市にも支部があります)で申請して取得することができます。
なお、不動産の相続登記については、相続放棄申述受理証明書に代えて、相続放棄申述受理通知書を提出しても、手続きを進めることができます。
参考リンク:裁判所・その他(相続放棄受理証明書)
3 残された相続人が複数である場合
残された相続人が複数人の場合、遺産を取得する人が誰であるかは、残された相続人の間で遺産分割協議が成立しない限り確定しません。
したがって、相続放棄が行われたことを証明する書類に加えて、残された相続人の間で遺産分割協議が成立したことを証明する書類も必要となります。
以上から、残された相続人以外の人についての相続放棄申述受理証明書(一定の場合は相続放棄申述受理通知書も可)に加えて、残された相続人が作成した遺産分割協議書、印鑑証明書を提出することで、不動産や預貯金の相続手続きを進めることができることになります。
遺産分割協議の内容を守らない人がいる場合はどうすれば良いですか? 相続放棄をした場合の死亡退職金に関するQ&A