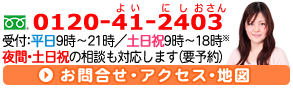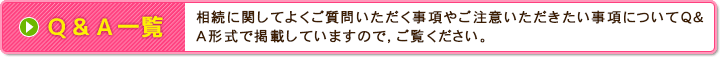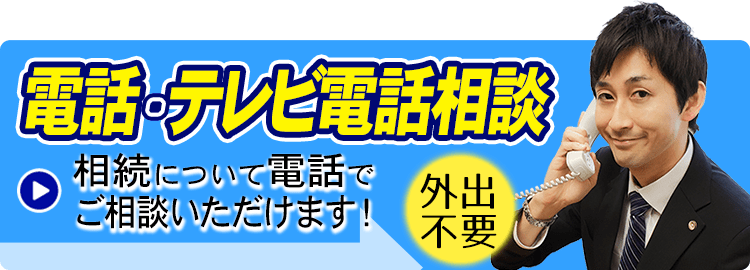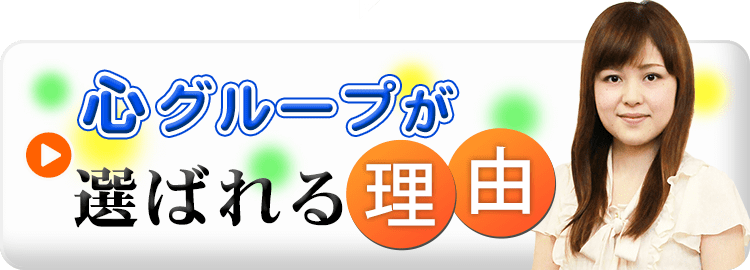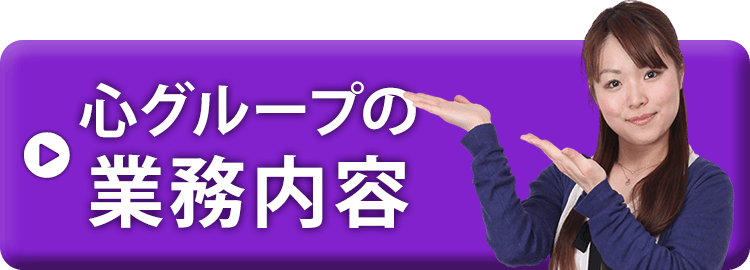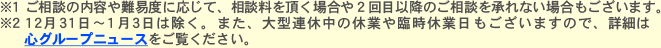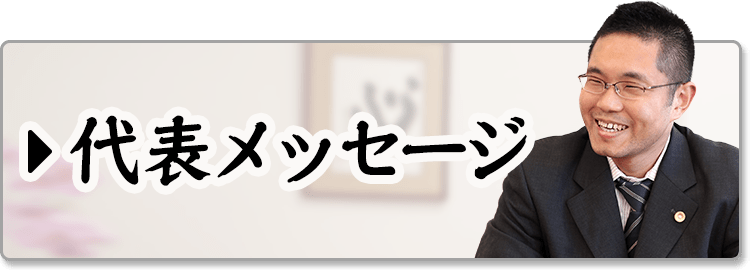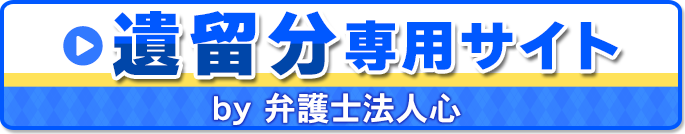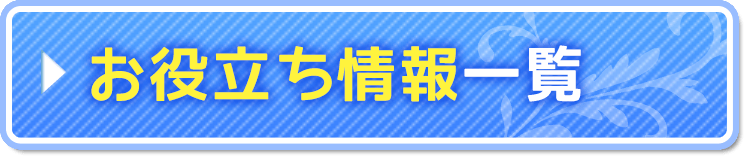相続における念書や誓約書の効力
1 念書や誓約書の効力
相続では、当事者間で何らかの合意に至った場合には、書面が作成されることが多いです。
作成された書面が遺産分割協議書、合意書等の形式になっており、内容面でも実体のあるものになっていれば、法的な効力が認められます。
他方、遺産分割協議書や合意書等には至らない文書であっても、一定の効力が認められる可能性があります。
2 合意書としての効力
まず、念書や誓約書についても、一定の場合には、合意書としての効力が認められ、記載された内容により、作成者に対する拘束力が発生する可能性があります。
合意書としての拘束力が認められる条件は、以下のとおりです。
① 合意内容を記載した体裁になっていること
念書や誓約書が、合意内容を記載した体裁になっていれば、合意書としての効力が認められる可能性があります。
当事者全員が署名を行えば、通常の合意書として扱われる可能性があります。
また、1人が署名した書面であっても、「約束します」「誓約します」等の文言が入っており、合意された内容を記載したものであることが明らかになっていれば、合意書としての効力が認められる可能性があります。
② 合意内容が明確であること
合意書としての拘束力が認められるためには、合意内容が明確になっている必要があります。
たとえば、「〇銀行の預金取得の見返りに、◯に対し、今後は誠実に接することを約束します」といった内容だと、どのようなことをしていれば誠実に接することとなるかが、明確になりません。
「〇銀行の預金取得の見返りに、◯の今後の生活を扶助することを約束します」も、作成者が扶養義務者として扱うという意味で、ある程度の拘束力はあるとは言えますが、いくらの金銭を支払えば扶養義務を果たしたこととなるのかが明確になっておらず、拘束力は限定的です。
「〇銀行の預金取得の見返りに、◯に対し、生活費として月◯円を支払います」といった文言であれば、合意内容を守っているかどうかが一義的に明らかになりますので、明確な拘束力が認められます。
合意内容が明確であれば、合意への違反があれば、法的手続をもって請求すること等も可能になってきます。
3 合意書としての効力の制限
ただ、念書や誓約書については、法的に権利義務がきちんと成立するかどうかを度外視して作成されることが、往々にしてあります。
このため、合意書としての効力が認められる場合であっても、一定の場合には、合意書の拘束力が制限されることがあります。
具体的には、以下のような場合には、拘束力が否定されてしまう可能性があります。
① 法律が予定している一定の手続を利用していない場合
たとえば、ある人Aの生前に、その人の相続人Bが、「私は、Aが死亡したとしても、一切の相続権も遺留分も主張しないことを約束します」といった書面を作成したとします。
このような書面については、法的な拘束力は認められません。
というのも、生前に遺留分を放棄する場合には、法律上、家庭裁判所の審判を得なければならないこととなっているからです。
このように、法律が一定の手続を利用することを予定しているにもかかわらず、その手続を利用せずに念書や誓約書だけを作成したとしても、法的な効力は発生しないこととなります。
② 合意内容が公序良俗に反する場合
合意内容が公序良俗に反するものである場合は、念書や誓約書は無効になります。
公序良俗に反するものとしては、様々なものがありますが、代表的なものは、違法行為を目的とするもの、人倫に反するもの、当事者に過度の負担を強いるもの等があります。
たとえば、特段の事情もなく、「今後、親の扶養義務は一切放棄する」といった条項を設けることは、人倫に反すると判断され、無効となる可能性があります。
他にも、資力、収入の裏付けがないのに、「今後、◯に対し、毎月100万円を支払う」といった条項を設けることは、過度の負担を強いるものとして、無効となる可能性があります。