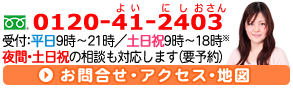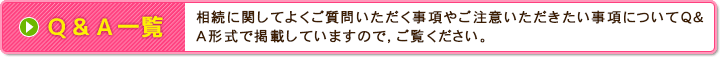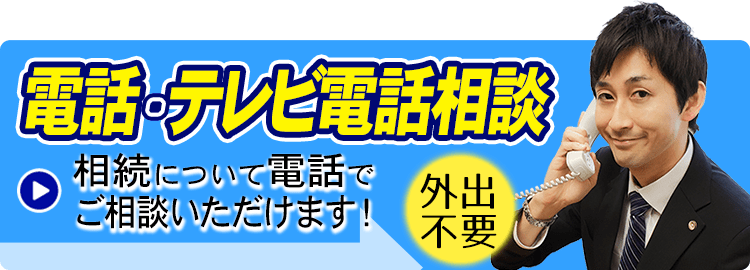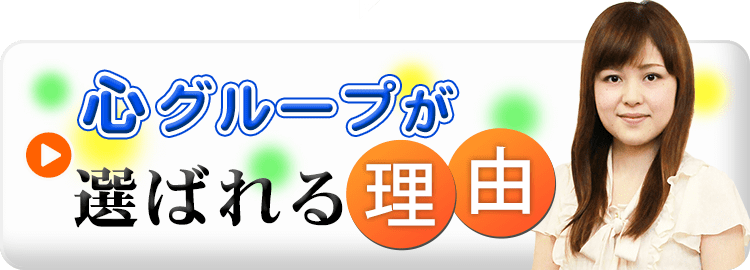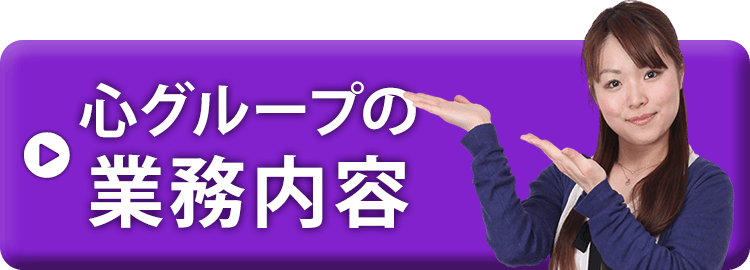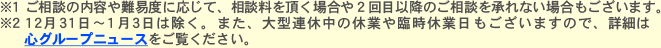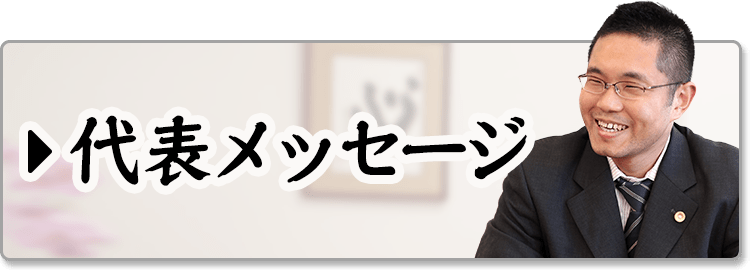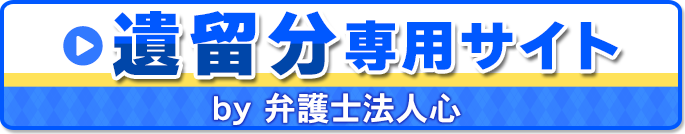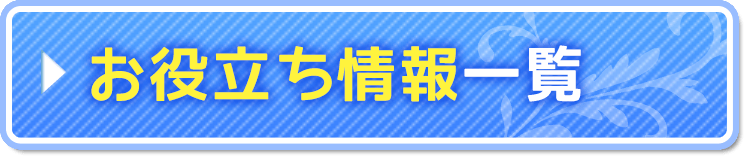相続人の廃除について
1 相続人の廃除とは
民法は、遺言で別段の定めがなければ、法定相続人に該当する一定の親族が、財産を相続できるとしています。
では、法定相続人に該当すれば、無条件に財産を相続することができるのでしょうか。
例えば、子が親に対して暴力をふるい、親に危害を加えたような場合であっても、子は当然に財産を相続することができるのでしょうか。
民法は、相続人の廃除の制度を設け、相続人となるべき者に一定の非行があった場合に、被相続人の意思により、相続権を喪失させることができるとしています。
2 相続人の廃除事由
民法は、次の3つを廃除事由として定めています。
① 被相続人に虐待をしたこと
② 被相続人に重大な侮辱を与えたこと
③ その他の著しい非行があったこと
審判において廃除事由に該当すると判断された事案は、多種多様です。
一例として、子が母の介護を元妻にまかせ、田畑を母に知らせないまま売却し、自分の所在を明らかにせず、母に対する扶養料も全く支払っていない事案で、廃除事由に該当するとした審判例があります(福島家審平成19年10月31日家月61巻4号101頁)。
判断が微妙なことが多いので、弁護士等に相談した方が良い場合が多いです。
なお、廃除の対象となる者は、遺留分を有する相続人に限られます。
これは、遺留分のない者(被相続人の兄弟姉妹)に遺産を承継させたくない場合は、遺言で相続分をゼロにする指定を行えばすみ、廃除を認める必要がないからです。
3 廃除の手続き
相続人の廃除事由に該当すれば、自動的に相続権を失うわけではありません。
相続人の廃除事由に該当する人の相続権を喪失させるためには、被相続人自身が、一定の手続を行う必要があります。
共同相続人ではなく、被相続人自身が一定の手続を行わなければならない点は、注意が必要です。
具体的には、以下のいずれかの手続を行う必要があります。
⑴ 被相続人自身が家庭裁判所で廃除の請求をする場合
被相続人は、家庭裁判所に、廃除の調停または審判の申立をすることができます。
管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
⑵ 被相続人が遺言によって廃除の意思表示をする場合
被相続人は、遺言によって廃除の意思表示をすることもできます。
この場合は、遺言執行者は、被相続人が亡くなった後、遅滞なく、家庭裁判所に廃除の請求をしなければならないものとされています。
遺言執行者でなければ、家庭裁判所に廃除の審判の申立てをすることができません。
このため、遺言書で遺言執行者の指定が行われていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる必要があります。
遺言執行者は、遺言の効力が生じた後、遅滞なく、家庭裁判所に審判の申立をしなければなりません。
管轄裁判所は、遺言者の最後の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所です。