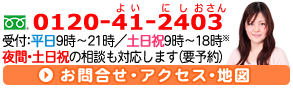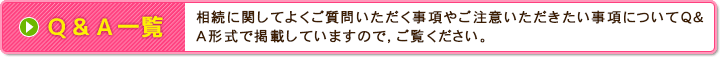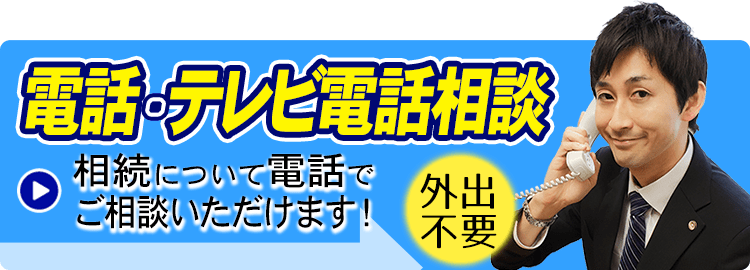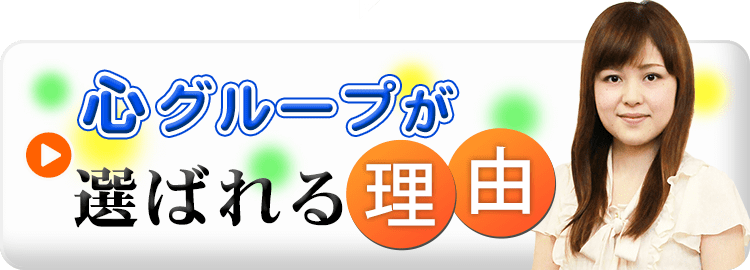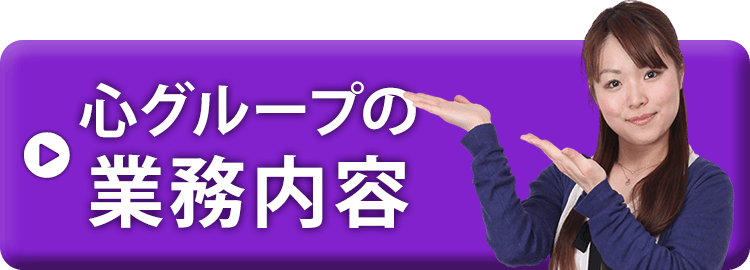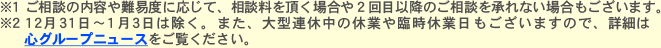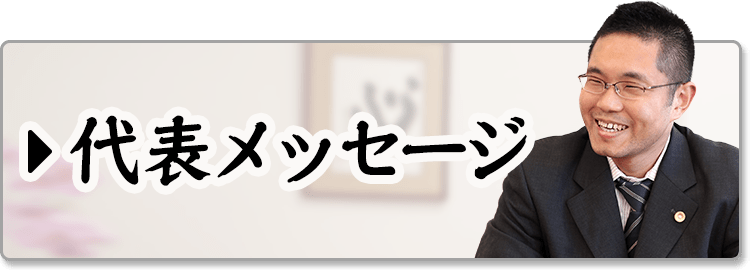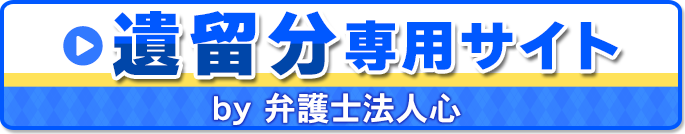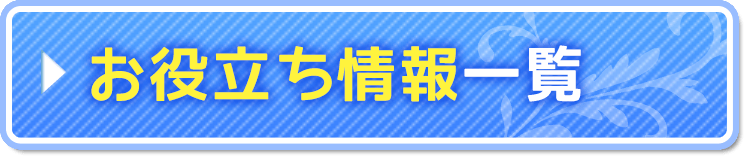相続税の税務調査の流れ
1 相続税の税務調査とは
相続税の申告を行うと、税務署は、提出された申告書の内容を確認します。
この申告内容について特に問題がなければ、問い合わせがなされることもなく、そのまま、相続税に関する手続きのすべてが完了します。
一方で、申告内容に問題があると税務署が判断した場合には、税務調査を行い、本来あるべき税額を確定する手続きがとられることがあります。
このように、税務署は、申告内容が適正なものであるかを確認するため、税務調査を実施することとなります。
ここでは、相続税の税務調査について、おおまかな流れを説明していきたいと思います。
2 金融機関等の調査
税務署は、実地調査に先立って、金融機関等の調査を行うことが多くあります。
具体的には、被相続人名義の口座について、過去にさかのぼって出入金記録を取得し、多額の出金がないかを確認します。
過去に多額の出金があった場合には、その出金が何らかの形で残っており、それが申告書から漏れているのではないかということを税務署が検討することとなります。
税務署は、被相続人名義の口座だけでなく、相続人名義の口座やその配偶者、子名義の口座等、親族名義の口座も調査することがあります。
これらを調査して、被相続人名義の口座から親族名義の口座に財産の移動があったかどうかを確認します。
財産が移動していたことが分かった際には、相続財産に含めるべきであると考えられる場合については、相続税の課税対象として扱われたり、贈与と評価するべきであると考えられる場合には、贈与税の課税がなされたりします。
また、親族名義の口座を調査することにより、名義預金が存在するかどうかの確認もなされます。
名義預金とは、名義は親族となっているが、実態としては被相続人が形成して管理していた預金であり、実質的には被相続人自身の預金であると考えられるもののことをいいます。
名義預金の調査にあたっては、銀行の届出印が同じか区別されているか、書類が被相続人によって作成されているか相続人によって作成されているか等の調査がなされます。
このような調査を経て、税務署は、実地調査で確認すべき事項のあたりをつけることとなります。
3 実地調査
その後、税務署は、相続人に対し、実地調査の日時や場所を指定したうえで、実地調査を実施することを通知します。
実地調査は、被相続人宅でなされることが多いですが、相続人宅でなされることもあります。
実地調査は、朝10時から始まります。
確認すべき事項が少ない場合は、1~2時間で終わることもありますが、夕方まで丸一日かけてなされることも多いです。
また、何日かに分けて調査がなされることもあります。
調査では、相続人に対し、様々な事項の聴取がなされます。
聴取した事項は、質問応答記録書という文書にまとめられることがあり、これに署名を求められることがあります。
質問応答記録書に署名すると、その後の手続きで、相続人が認識していた事項を記載した書類として扱われ、これを根拠に重加算税の課税がなされることもあります。
質問応答記録書に署名してしまうと、あとで勘違いだったと言って、質問応答記録書を撤回することを求めることは困難ですので、署名する際には、記載内容を十分に確認し、誤りがある場合は訂正を求めた上で行うべきです。
こうした聴取以外にも、金庫を見せてほしい、通帳を見せてほしいと求められることがあります。
金庫を確認することにより、金庫内に、申告書から漏れている通帳や証書があるかどうか、財産をまとめたメモ等があるかどうか等の確認がなされることがあります。
また、通帳を確認することにより、手書きで贈与等の事実が記載されていないか等の確認がなされることがあります。
このように、実地調査では、特定の場所、特定の物を確認したいという話が出てくることがあり、これにより、申告漏れの端緒となる情報の取得がなされることがあります。
4 修正申告
実地調査が完了してから何週間かあとに、税務署から調査の結果が告げられます。
この時、税務署からは、調査の結果確定された申告漏れ、計算間違い等の指摘がなされ、税務署が考える適切な申告内容が告げられます。
この税務署が考える適切な申告内容に基づき、相続人の側で修正申告を行うかどうかの判断を行うこととなります。
相続人が修正申告を行うこととした場合には、相続人は、修正申告書を提出し、追加の税金の納付することとなります。
また、加算税、延滞税についても納付することとなります。
相続人が修正申告をすることに同意しなかった場合も、これで終わりとなるわけではありません。
税務署の側から、税務署の結果を踏まえた更正処分がなされ、やはり、追加の税金、加算税、延滞税の納付を行わなければならなくなります。
相続人の側で更正処分の内容に不服がある場合は、国税不服審判書への不服申立、引いては税務訴訟の手続きを行うかどうかを検討することとなります。
相続税申告において贈与税の申告がされていない場合の対処 相続税を申告・納付する義務がある人